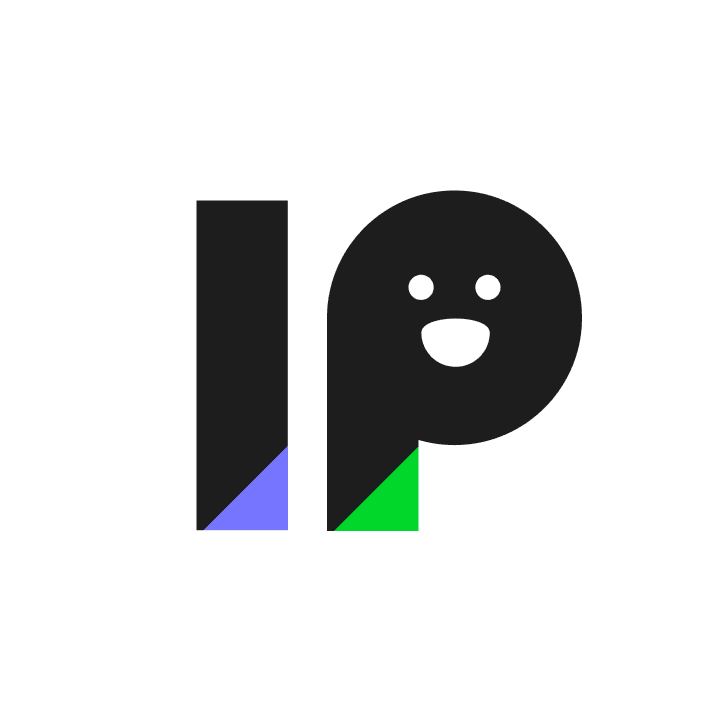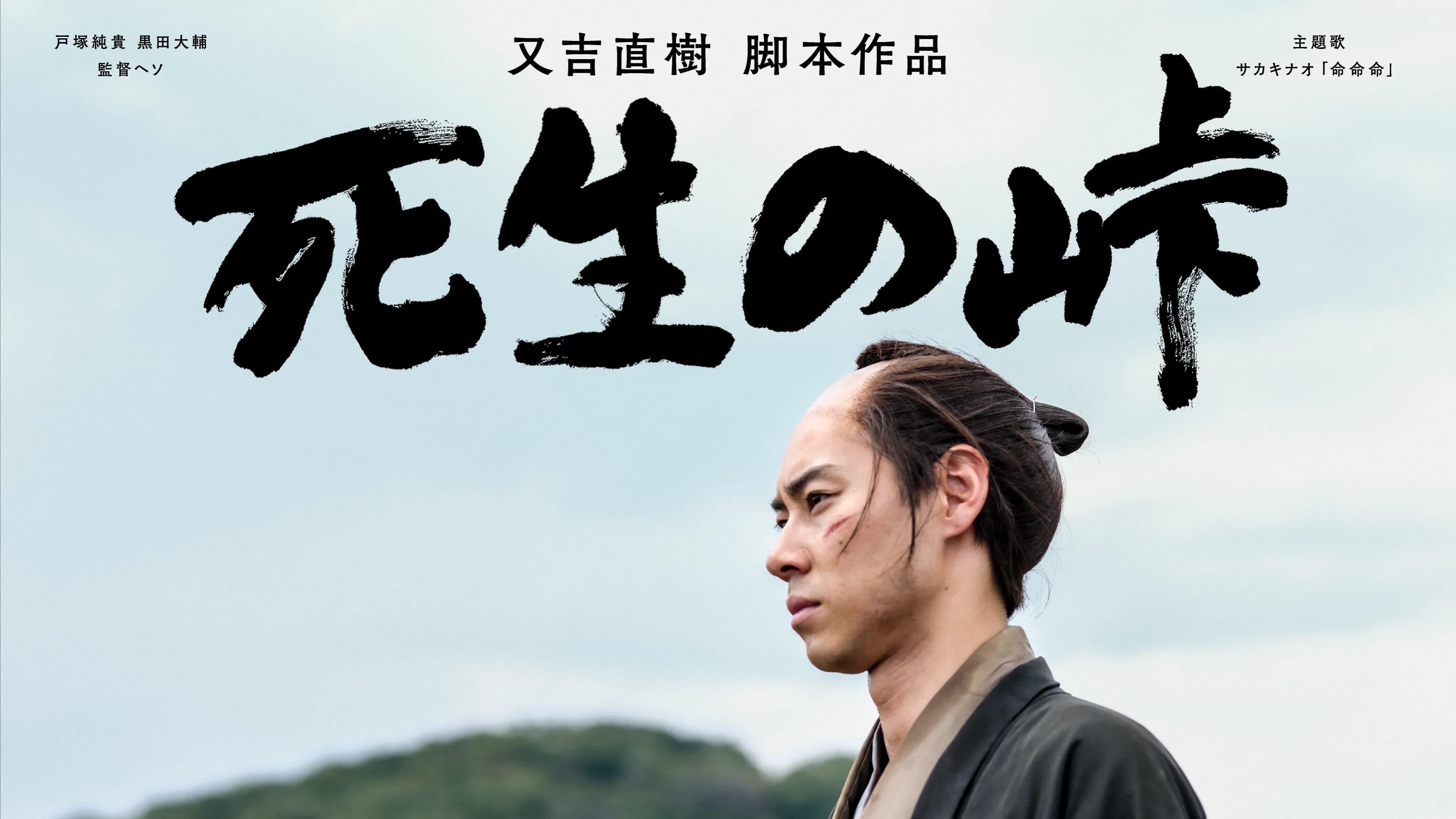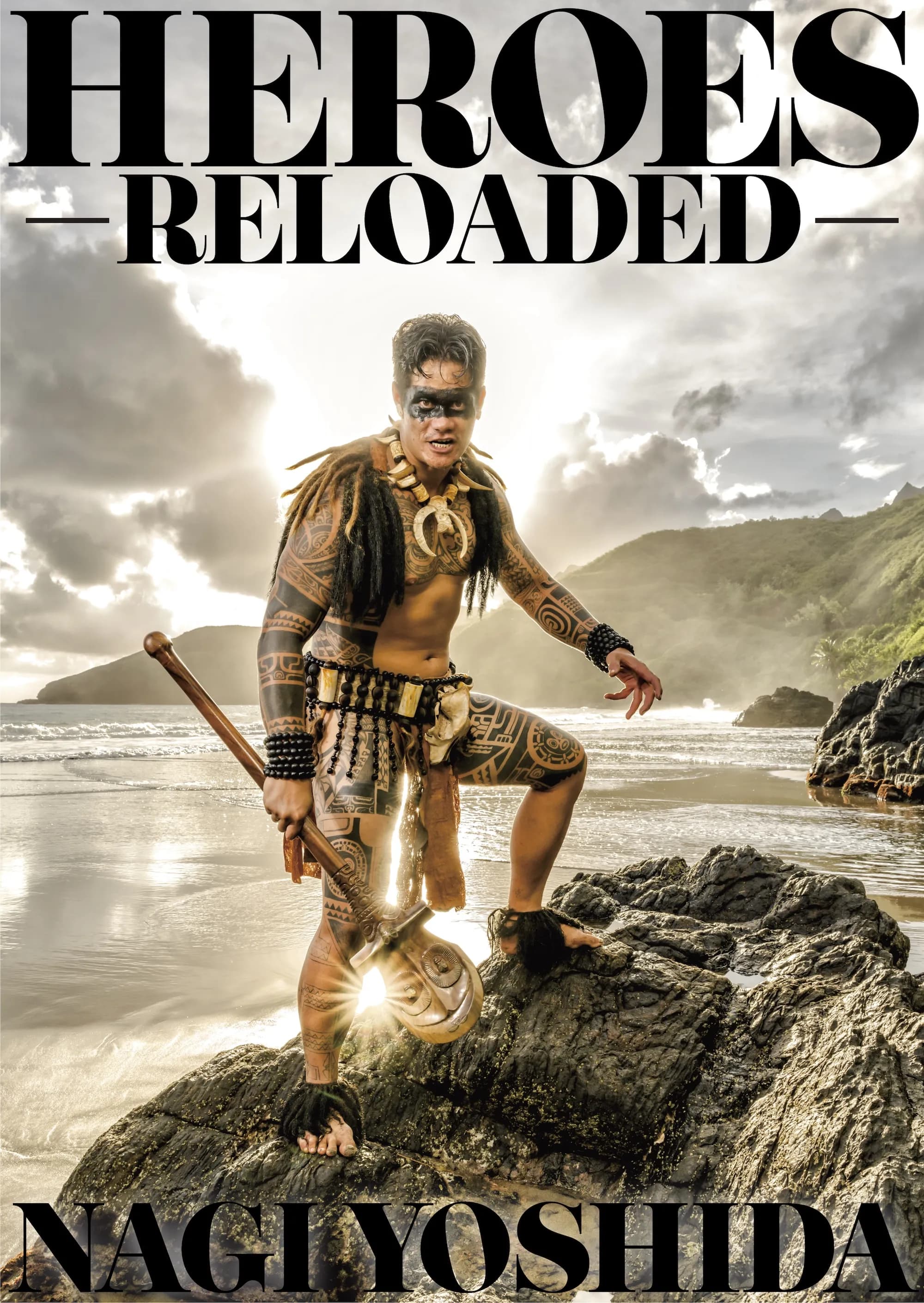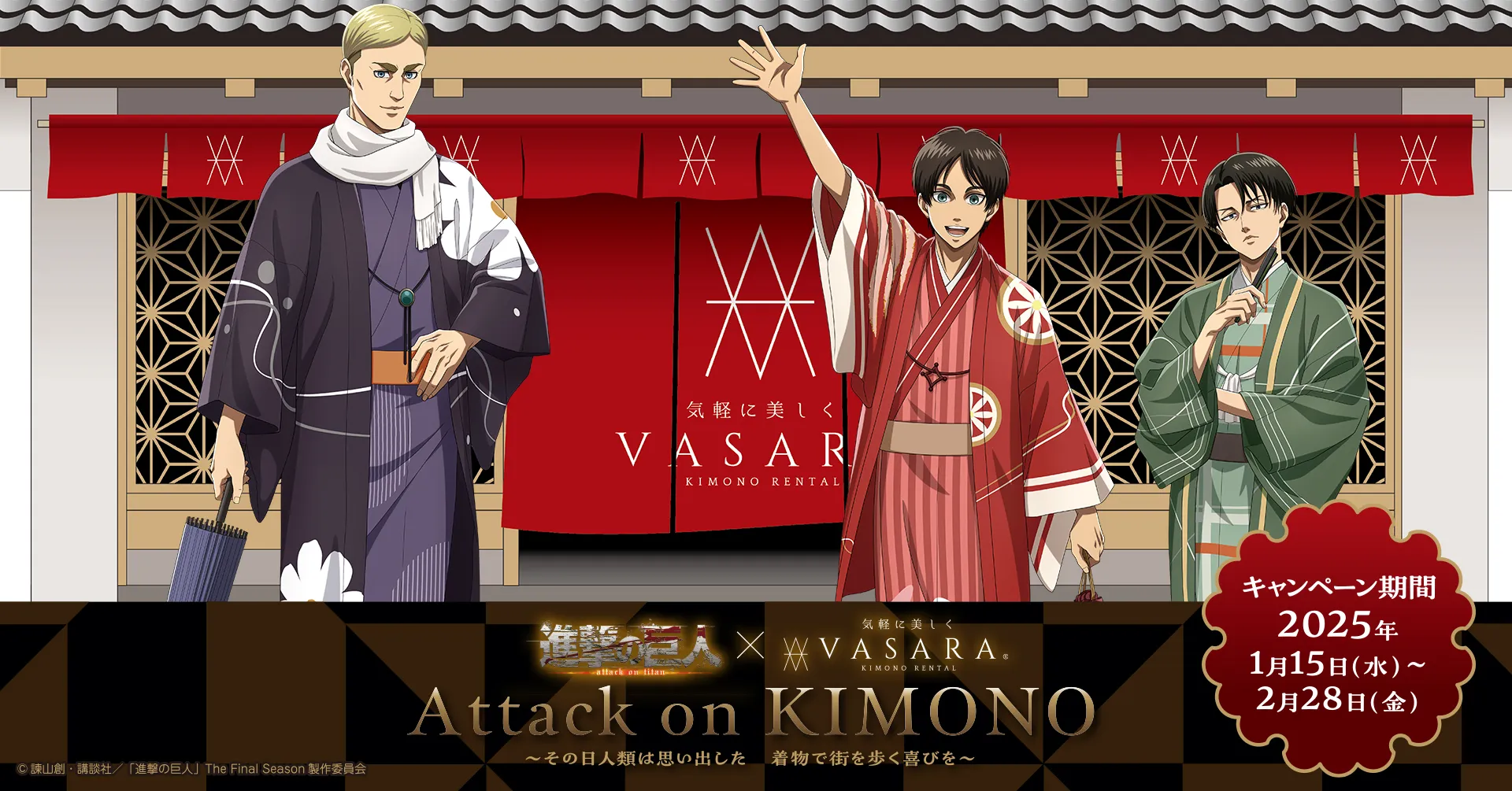東京生まれ、渋谷ラバー。2011年小説『空のつくりかた』刊行。その後アパレル企業のコピーライティングをしたり、webメディアを立ち上げたり。最近の悩みは、趣味が多すぎてなにも極められないこと。でもそんな自分が好きです。

バーチャルヒューマンimma(イマ)、AI搭載によりリアルタイムの対話が可能に
当記事は対話型AIバーチャルヒューマン「AI imma」日本語対応版のメディア体験会に取材訪問し、作成いたしました。
immaといえば、アジア初のバーチャルヒューマン。SNSの総フォロワー数は100万人以上、Forbes Womenの「Women of the Year 2020」に選出され、パラリンピックの閉会式に登場、そして2025年の大阪・関西万博のスペシャルサポーターに就任と、実在しないというのに、すでに人気も評価も獲得しているインフルエンサーです。
当メディア「IP mag(アイピーマグ)」では以前、そのプロデューサーであるジューストー沙羅さんへインタビューさせていただきましたが、そのときに触れていた「AI imma」がついに実現したということで、本日2024年12月9日(月)に行われた体験会に参加してきたので、その様子をお伝えいたします。
登壇されたのは、株式会社Awwの代表取締役である守屋貴行さんとエヌビディア合同会社の中根正雄さん。

国境を越えるバーチャルヒューマンimma(イマ)プロデューサーSara Giusto
immaとは?

immaとは、今や国内外問わず世界中で人気を集めるバーチャルヒューマン。ピンク色の髪がトレードマークで、さまざまなブランドや企業とコラボしています。最近だとグローバルファッションブランドのCOACH(コーチ)のグローバルキャンペーン“Find Your Courage”をご覧になった方も多いのではないでしょうか。
生み出したのは株式会社Aww。といっても、実は会社が立ち上がったのはimmaちゃんが誕生した翌年。その後、同社は数々のバーチャルヒューマンを世に輩出しつづけ、2023年よりAIとの融合を開始させました。
そして2024年にNVIDIAとの提携を発表。バーチャルな存在ながらTED Talkに登壇したのもこの年です。くわしくはimmaのプロデューサーであるジューストー沙羅さんへインタビューにて語られているので、こちらの記事もご覧ください。

国境を越えるバーチャルヒューマンimma(イマ)プロデューサーSara Giusto
AI搭載でimmaちゃんとリアルタイムで対話ができるように
上は筆者がAI immaを実際に体験したときの映像(かなりスタッフの方に助けていただいていますが……)ですが、人間同士の対話と同じくらいのスピードで返答されることに驚きます。
体験会のなかでは他記者の「なにを話せばいいかわからない……」という独り言さえばっちり拾って、「それじゃあ趣味の話でもする?」とimmaに提案される場面もあり、そのホスピタリティにも感動。
「会話を続ける努力」は、人間同士特有のコミュニケーションの取り方だと思っていましたが、AIにもできるようになってしまいました。
今回披露されたAI immaは日本語版ですが、実は英語版のほうが開発が進んでいるらしく、よりスムーズな会話を楽しめるとのこと。もしかしたら英語の勉強にも活用できるかもしれません。

AI immaの特徴はやはりその人間に近いビジュアル。AIが搭載される前から、他のバーチャルヒューマンとは一線を画すほどのリアルな質感を再現していましたが、こうしてリアルタイムで対話できるようになると、より一層人間らしさを感じます。
株式会社AwwはキャラクターIPを強化すべく3DCG技術を駆使して、immaの造形を作り上げました。だからこそさまざまな雑誌の表紙を飾ることができたり、ブランドのアンバサダーに選ばれたりしているのでしょう。
そしてもうひとつの強みは、プログラミングされた言語を話すのではなく、過去の自身のSNSへの投稿などから学習した内容をもとに人間と対話をするという点。これを実現させるにはNVIDIAの持つ最先端のAI技術が欠かせませんでした。
すでに完成されていたimmaのイメージを損なうことなくコミュニケーションを取ることができるので、普段SNSなどで見かける彼女の解像度をより上げることができるでしょう。
バーチャルヒューマンだからできること

Emergen Research社によると、世界のバーチャルヒューマンアバター市場は、2022年の295.1億ドルから2032年までに5,611億6,000万ドルに達すると予測されています。
この中にimmaのようなバーチャルインフルエンサーがどれほどふくまれるかはわかりませんが、今後バーチャルヒューマンがあらゆる業界において、より一層存在感も注目度も拡大していくことは必至といえるでしょう。
バーチャルヒューマンが注目されるポイントは、オリジナルキャラクターとしての資産性を保ちながら人間の共感性も得やすいところにあると守屋さんは言います。
リアルタレント | マスコットキャラクター | バーチャルヒューマン | |
|---|---|---|---|
資産性 | × | ◎ | ◎ |
コンテンツ拡張性 | △ | △ | ◎ |
共感性 | ◎ | × | ◎ |
持続性 | × | ◎ | ◎ |
(表の内容は体験会の中で発表されたものに則っています)
バーチャルヒューマンはなにも、見た目が人間に近ければ共感性を得られるわけではありません。そこには彼、彼女のバックグラウンドや意識、感情といった「ストーリー」が必要です。また同時に世界視点で捉えられる視座を持つことで、グローバルIPとして存在感を確立することができるのです。
守屋さんは、バーチャルヒューマンが店舗などの接客、コールセンターの対応などを担うことで、深刻化する人手不足問題に一手を打つことができるのではないかと期待を明かしていましたが、それが人々の共感を集めることのできる存在であれば、なおさら我々の生活に密に寄り添う未来が見えてくるようです。
当記事は対話型AIバーチャルヒューマン「AI imma」日本語対応版のメディア体験会に取材訪問し、作成いたしました。