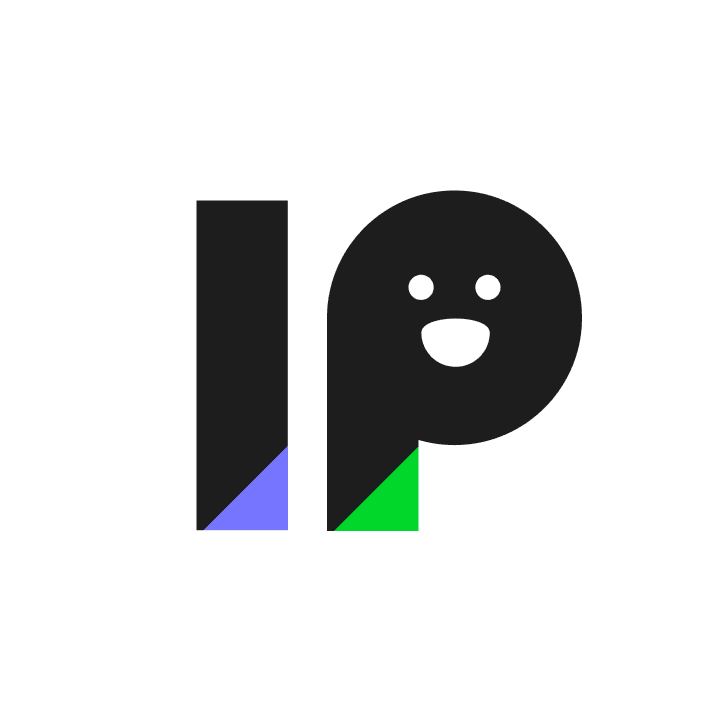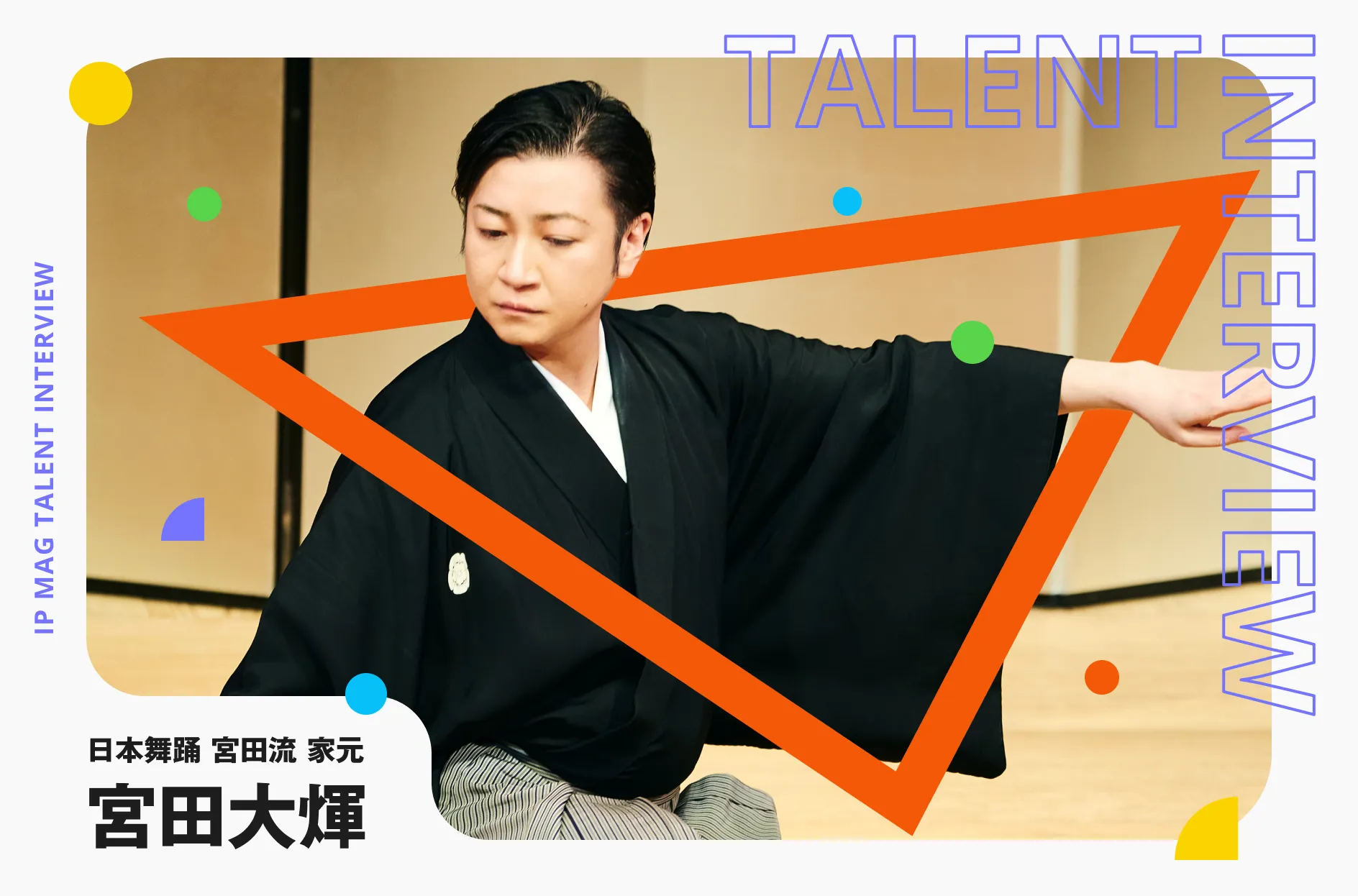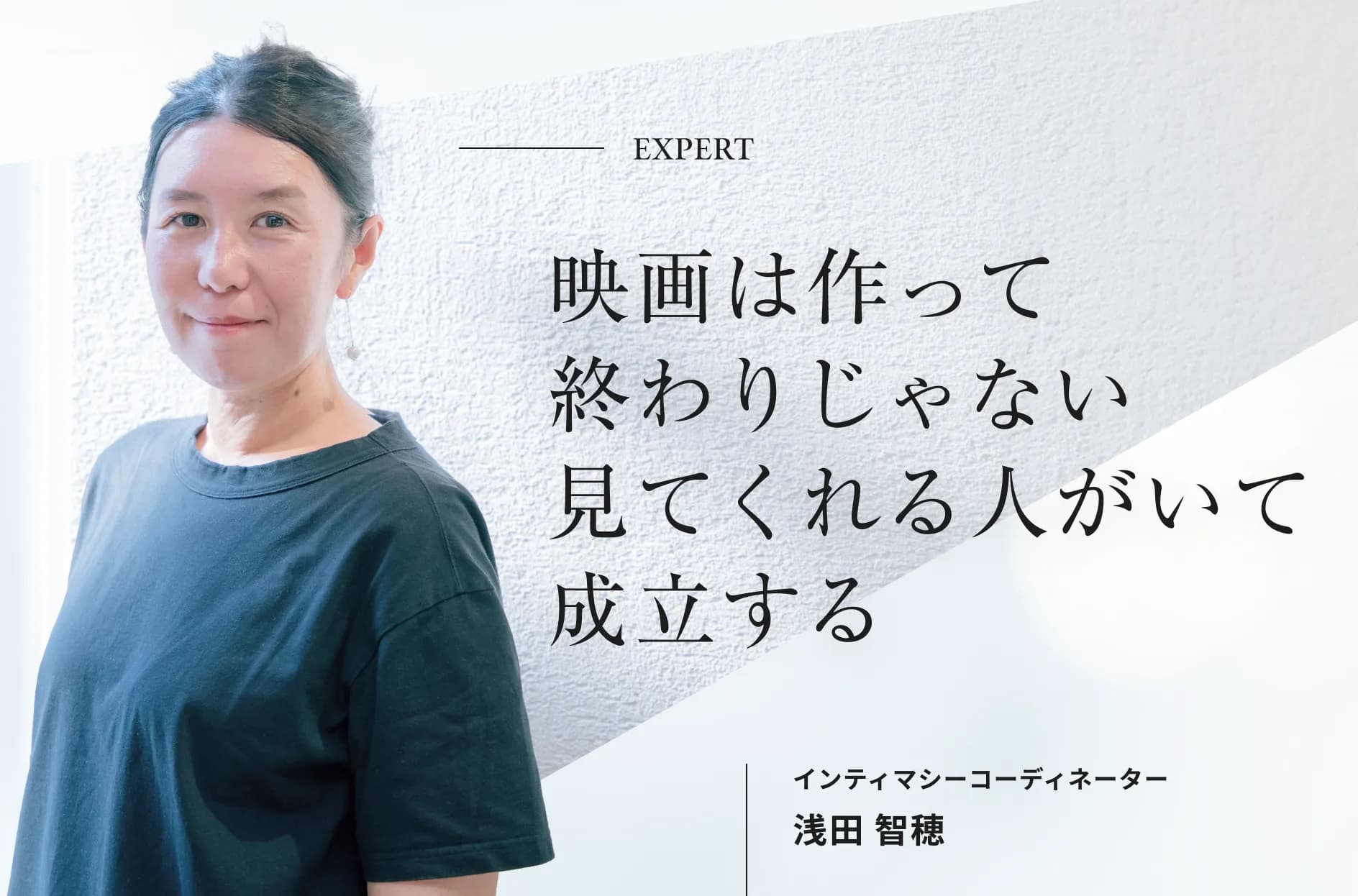東京生まれ、渋谷ラバー。2011年小説『空のつくりかた』刊行。その後アパレル企業のコピーライティングをしたり、webメディアを立ち上げたり。最近の悩みは、趣味が多すぎてなにも極められないこと。でもそんな自分が好きです。

2度目のグラミー賞受賞なるか?宅見将典(Masa Takumi)さんの戦略と成功の軌跡
2023年の第65回グラミー賞において、『Sakura』というソロアルバムが最優秀グローバル・ミュージック・アルバム賞を受賞した宅見将典さん(Masa Takumi名義)をご存じでしょうか。この部門賞を日本人が受賞するのは初めてという快挙でした。
宅見さんは2001年にロックバンドsiren(サイレン)のメンバーとしてメジャーデビュー後、作曲や編曲、数々のアーティストのプロデュースを務め、国内外で多くの賞を受賞しています。
その一部を挙げると、日本レコード大賞において、2011年の第53回には作曲をしたAAAの「CALL」が、その8年後の第61回には作曲、編曲を手がけたDA PUMPの「P.A.R.T.Y~ユニバースフェスティバル」が優秀作品賞を受賞。
2023年には文化庁長官表彰(国際芸術部門)、そしてNewsweekによる「世界が尊敬する日本人100」に選ばれ、2024年には第53回ベストドレッサー賞(インターナショナル部門)を受賞しました。
国外においては、2014年にSLY&ROBBIE and THE JAM MASTERSのメンバー(G,Key)として制作したアルバム『REGGAE CONNECTION』が第56回グラミー賞ベストレゲエアルバム部門にノミネート。これ以降、グラミーボーディングメンバーとなります。
またソロアルバム『Deep Down』『Heritage』などが米国のThe Akademia Music Awardsを受賞、Hollywood Music Media Awards (HMMA) 、Global Music Awardsといった数々の米国内アワードにノミネート。
さらに、きたる2025年の第67回グラミー賞においては、ソロシングル「Kashira」が最優秀グローバルミュージックパフォーマンス部門にノミネートされ、2度目のグラミー賞受賞が期待されています。
こんなにも華々しい経歴を誇るので、生まれもっての天才肌のアーティストを想像するかもしれませんが、宅見さんご自身は今回のインタビューのなかで「2023年にグラミー賞を受賞していなければ、今みたいに笑顔で人と会えなかったかもしれない」と語ります。
また「グラミー賞受賞」という夢を掲げてからは、「もしも」の想像はせずにまっすぐ前を向いて邁進してきたため、逃げ場もなく死に物狂いだったと振り返ってもいました。
「天才とは努力を続けられる人のこと」とはよくいいますが、宅見さんこそまさしくそれを体現し、自らの手で夢を叶えた人かもしれません。
- 原体験は狭い部室で聞いた大合奏の倍音
- バンドsiren始動、メジャーデビューを目指した理由は「MVを撮りたいから」
- 「今の自分がsirenをプロデュースするなら」という夢ばかり見る
- 音楽におけるアメリカと日本のトレンドの違い
- 独学だからこそ身につくことがある
- ターニングポイントはグラミー賞授賞式とEXILEの……
- 逃げ場を作らずギリギリの状態で掴んだ「グラミー賞受賞」への道
- 2度目のグラミー賞受賞のチャンス。今の心境は?
- 「グラミー賞2025」を音楽家としてのひとつの区切りにする
- 時流には逆らわず、逆手にとる

原体験は狭い部室で聞いた大合奏の倍音

早速ですが、音楽活動を始められたきっかけについてお伺いできますか?
最初のきっかけは小学4年生のときに吹奏楽部に入ったことです。トランペットを担当していたんですが、やっぱり初めて体験する生楽器の合奏は感動もので、そこからモチベーションが上がったという感じですね。
トランペットを選ばれたのはどうしてですか?
先生に指定されたんですよ(笑)。子どものころって楽器に関する知識もないし、僕としては「とにかく叩けば音が鳴る」というイメージで打楽器、ドラムがよかったんですけど。
金管楽器は音が鳴るまで3か月くらいかかるのかな。子どもにとっては演奏できるようになるまであまりにも長くて、なのでドラムは取り合いでしたね。一番不人気だったのはチューバ。唇の筋肉を使うし、大きいから子どもには扱いづらくて。
大人になった今は、子どものころ簡単に見えていたタンバリンも演奏してみるとすごく難しいっていうのを知っていますし、楽器の難しさは全部一緒だと思っています。
そのうえで当時メロディーを担当できてよかったですね。おかげで譜面を読めるようになりましたし、そのときの体験から、作曲するときにメロディーを一番大切にするようになりました。
チューバではないんですが、私も子どものころに吹奏楽部でユーフォニアムを吹いていて、その大きさと重さに慣れず、途中でフルートに変えた記憶があります……。素敵な音なんですけどね。
ユーフォニアムはトランペットと指遣いが一緒なので僕も吹けますよ。でもいい音なんですけど、あまりチューバもユーフォニアムも大編成ではない限り、日本でレコーディングするときにオーケストラに入れないかもしれません。
日本でサウンドトラックを制作する際に一般的には起用しないと聞いたことがあります。僕自身は結構チューバの音が欲しいなと思うんですが……。
でもそういう僕のオーケストレーションの考え方も、あの狭い部室で大合奏したことが原体験として身についているんだろうなと思いますね。
やっぱりあの倍音を小さいころに大音量で体験できたっていうのは、未だに記憶にもすごく残っているんです。なので、それが自分の音楽人生のスタートかなと思います。
バンドsiren始動、メジャーデビューを目指した理由は「MVを撮りたいから」

そこから時を経てロックバンドsiren(サイレン)のメンバーとしてメジャーデビューされますが、そのときの道程についてもくわしくお聞きしたいです。
中学生になってからロックバンドを組んで、そのときの記憶がのちのsirenの活動にもつながっていくんですけど、音大時代にいいメンバーと出会ってバンドを組み、「一緒に東京に行こう」と上京して、それですぐにデビューできたんですよ。「大阪出身のバンドでは最短」って言われたくらい。
当時はメジャーとインディーズの間に大きな壁があって、たとえばインディーズバンドはMVなんて撮れませんでした。インターネットもなく、メディアといえばテレビ、雑誌、ラジオという時代です。
コンピュータはありましたけど、メモリ容量があまりに少なくて、今みたいに個人で動画を撮って編集するなんて考えられなかったですね。そもそも映像を取り込むどころか録音もできませんでした。
でも外部の機材をつなぐことはできたので、サンプラーとかほかにもいろいろ機材をつないで音楽を作っていました。
そういう作業やバンド活動のほうが大学よりも楽しく感じてきて、どんどん比重が傾いていき、本格的に音楽一本に絞ったところでのデビューだったんですけど、当時の僕にとってメジャーデビューしたい理由は「MVを作れる」とか「テレビに出られる」とか、そういったものでしたね。
でもデビューするのも早ければ、終わるのも早くて……。結成から4年、メジャーデビューしてから2年で僕だけ脱退したんです。
その後もバンドは名前を変えて続くんですけど、自分がsirenを壊してしまったと思っています。プロデューサー感覚で仕切っていたんですよね。メンバーを集めたのも自分、曲を作るのも自分、上京しようって決めたのも自分だったので、大人たちも口出しできなかったんだと思います。
全然人の話を聞かなかったので、やっぱりみなさんの意見も聞かないとだめだなと。あとから、僕が意見を聞かないからどうしようって考える会議があったと聞きました。
「こういうプロデューサーを呼んだら話を聞くんじゃないか」と呼ばれてやってきた人とも喧嘩するし、とにかくすごく尖っていたんです。
ご自身がメンバーを集めたり、決断したりしているっていう責任感からプレッシャーを感じていらっしゃったのでしょうか?
「自分たちの音楽を守らないといけない」っていう思いはありました。当時は今以上に大人たちの力が強くて、警戒心が強かったんですよね。
「今の自分がsirenをプロデュースするなら」という夢ばかり見る

でも脱退して3か月くらい経ったら、あんなに周りにいた大人たちはだれもいなくなっていて、「なんだったんだろう、あの人たちは?」と思いましたね。
デビューしてすぐにバッとやってきて、売れないとわかったらバッと離れていって……、なんだか夢を見ていた気持ちになりました。それで現実に返って「地に足をつけてちゃんとやろう」と、「作曲家として一からやり直そう」と思ったんです。
今となってはそんなに若いうちに、しかも早い段階で大きな失敗ができてよかったと思います。ほかのメンバーには本当に申し訳ないですけど、僕自身はバンド活動を経て、自分の夢がそれではなかったことに気づけました。
活動中も「オーケストラどうしよう」とか「シンセ(シンセサイザー)どうやって入れよう」ということばかり考えていたので、バンドマンというよりもプロデューサーに近い感覚だったんですよね。
本来そういうことはそれこそ大人に任せて、バンドマンはドラムならドラム、ギターならギター、と自分たちのパートにもっと集中してシンプルな構造で音楽を作るほうが、オーディエンスの求めるものになるんですよ。
でも僕はそういうノリとかを全然考えずに装飾というかアレンジメントばっかり考えちゃって……。それもあってテンポが遅い曲ばかり作っていました。
バンドってやっぱりキメ(※)があったり、テンポが速かったりするサウンドが多くて、なのでほかのバンドと対バンしたときも、僕らだけゆっくりした曲が多くて「どう乗っていいかわからない」って言われることもありました。
※ キメ:楽曲内の特定の箇所を奏者全員がタイミングとリズムをそろえて演奏をすることで、効果的にアクセントをつける手法。 |
|---|
今の自分がもしあのころの自分に会うことがあれば……っていう夢ばかり見るんですけど、もし僕がsirenのプロデュースをできるなら、ああしたい、こうしたい、そうしたらもっとよかっただろうなって考えます。
もちろんそういう失敗が今に結びついているから後悔ばかりではないんですけど、でもやっぱりずっとつきまとっちゃいますよね……。
もしプロデュースできたら、たとえばどういう点を変えますか?
やっぱり「テンポは上げなさい」って言いますね。あの当時、テンポの速いエモーショナルな音楽ってあまりなくて、切ない曲ならゆっくり、速いならメロコアというのが主流だったんですけど、テンポを上げてそういう曲調をやってもいいんだよって伝えます。
「むしろありふれていないからこそいいのに」って今は思いますけど、当時は保守的で、流行っていないものをやることの怖さを感じていたんですよね。
あと「オーケストラとかバンド以外の弦とかは忘れて、まずバンドメンバーのギターとベースとドラムだけでアレンジを考えなさい」とも言います。可能性なんて無限にあるのに、なぜか「ほかに楽器を入れないといけない」と思い込んでいたんですよね。
音楽におけるアメリカと日本のトレンドの違い

そんなこと言って、今も速い曲はほとんど作っていないんですけどね(笑)。まぁ今はいいのか、バンドじゃないので。サウンドトラックでもないソロ名義の、しかもインスト曲で速くする必要はないですもんね。
しかもソロ作品の場合は主にアメリカのオーディエンス向けに制作しているんですけど、向こうはどんどんテンポが遅くなっています。10数年くらい前からBPM128のEDMが流行り、そこからどんどん遅くなっているんです。
というか、遅くないと出せない帯域があるんですよ。ヒップホップの場合、「808」っていうシンセサイズされたベースサウンドを使うのが基本なんですけど、キーとテンポがある程度決まっているんです。そうでないと、求めている音像にならないといいますか……。
日本の曲にそういう帯域がないのは、速い曲が多いからなんです。やっぱり軽快な曲って低音が入っていても、ヒップホップみたいに「ズン、ズン」っていう音は鳴らないじゃないですか。
ジャンルによって帯域が違うっていうのは渡米してから知ったんですよね。そこから「テンポとキーってここまで重要なんだ」っていう気づきが、自分の作品にも投影されていきます。
実は昔一番おざなりにしていたかもしれない部分なんですけど、いろんなことをやってきて、結局原点に立ち返るとそのふたつがすごく大事なんですよね。今はそこを決めるのにすごく時間をかけています。
昔だれかに教わったとしても、当時は人の話を聞くような性格ではなかったから、自分で気づいたことで、より深くまで理解することができたという気がします。それこそ今まで教えてくれた方々への感謝の気持ちも自然と感じました。
すごく時間がかかったんですけどね(笑)。だから今、本当の意味で音楽家として、やっといろんなことをできるようになったんじゃないかなと思います。
独学だからこそ身につくことがある
僕が交流のあるアメリカのミュージシャンは大抵、複数の楽器を弾けます。ひとつしか弾けないっていう人をあまり見たことがないかもしれません。
音楽に向ける知的好奇心が強い傾向にあるのでしょうか?
僕の場合はまさしく好奇心のみで「これやりたい」「あれやりたい」ってどんどん弾ける楽器を増やしていったんですけど、ほかの方はどうなんでしょう?どんな環境で音楽を始めたかにもよるかもしれません。
でも、うまくなる方法を見つけるのが早いのかもしれないですね。日本にいると、ギターを弾けない男性によく「俺、指短いねん」って言われるんですけど、だいたいそういう方って僕より指が長いんですよ(笑)。

自分で自分の形に合ったアジャストメントを探す能力が高いかどうかってことかもしれません。
日本の場合、基礎を学ぶことを重視する傾向にあるので、ちゃんと先生に習うことを推奨する方も多いですよね。もちろん基礎を学ぶことは大事だし、たとえば世界的なピアニストを目指すのであれば、そうしたほうがいいと思いますが、そこを目指していない人もたくさんいるよなぁと。
アメリカはあまりそういう習慣がないんですよね。僕もセルフトートでだれにも習っていないです。とくにクラシック文化がそこまで根付いていないので、セッションスタイルで音楽に触れる機会が多い気がします。
中部、南部ではギターはそこら中にあるし、ピアノもアップライトなら見かけるし、楽器に触れる機会が日本より多いんじゃないですかね。
だから興味も持ちやすいし、あとやっぱり自分の体に合う弾き方を探る能力が高いんだと思います。弾けなくても諦めずに「こうしてみよう」「ああしてみよう」ってプランB・Cを試してみるといいますか。
トライアンドエラーを惜しまないということですね。
そうですね、僕自身の人生がそうなので(笑)。エラーもしんどいですけどね。でも僕の場合は、吹奏楽部の休憩時間に友だちのパートと交換してドラムを叩いてみたり、親に頼んでギター、ベースを買ってもらって、ひとりで弾いてみたっていうのが結果としてよかったのかもしれません。
お話を聞いていて、日本と海外のストリートピアノの扱いの違いを思い出しました。日本だと上級者がテクニックを披露するステージになりがちですけど、それもよりよいパフォーマンスを生み出す場として機能していますが、海外だと経験のない方も気軽にぽろんって弾いていて、まさしく楽器に触れる機会になっていると感じます。
音楽を楽しんでいるっていう感じですよね。よく“be yourself”っていう言葉を聞きますし、自分自身を尊重していれば、それに対してだれもなにも言わない環境なんですよ。
楽器だけではなく踊ることに対しても、親は隣の家の子と自分の子を比べないし、もともとエンターテインメント領域の能力を伸ばす環境が日本よりあるのかもしれないですね。もちろん個人差はあるので、あくまで傾向の話ですけど。
ターニングポイントはグラミー賞授賞式とEXILEの……

音楽業界のさまざまな分野でご活躍されていますが、ご自身の音楽人生において一番転機になったと思う出来事はなんですか?
やっぱり初めてグラミー賞授賞式を見に行ったときですかね。そこで人生観が変わって「グラミー賞を受賞する」という夢を掲げるようになったんです。
でもそこに行く大きなきっかけになったのは、まだ20代のころにEXILEの「変わらないモノ」(2007年)という曲を作ったことですね。超メジャー級のアーティストに曲を書いたのは初めてだったんです。
それでATSUSHIさんとTAKAHIROさんに歌っていただいて、おふたりの歌の力によって曲の魅力がぐんと上がったと感じました。
とくにATSUSHIさんの歌声を聴いたときに、自分に本来以上の才能があると錯覚してしまうくらい、曲の魅力をすごく引き上げてもらったんですよ。仮歌の時点で、自分の価値観が大きく変わって自信がつきました。
そこで、一音に対してひとつの文字しか入れられないっていう自分の譜割の悪い癖に気づいて「歌だからもっと変えてもいいんだ」って自由度が広がったんです。
その後いろんな人と仕事できるようになったときに、あるチャンスをもらって、現地でグラミー賞授賞式を見ることになりました。
なんというか、人間を超えた、人間とモンスターの間のフィジカルと歌声を感じましたね。あと消防法が日本と違うので、演出に使う火力も全然違うんですよ。
いってしまえば、世界の紅白歌合戦という感じですけど、どのアーティストも日本に来日したら1人、もしくは1組でドームを埋めてしまうような人たちです。
そんな方々のショーを同時にいくつも見られるんですよ、しかも立て続けに。そのうえでアリーナ席ではスーパースターが談笑していたりして……、とにかくすべてに大きなショックを受けましたね。
このときに「もう1回ここに戻ってきたい」と思って、グラミー賞受賞の夢を掲げるんです。だから帰国してすぐ、その日のうちに英会話の本を買いに行って、翌日くらいには英会話スクールに申し込んでいました。
やっぱり成功されている方は、決断と行動が早いですね。
じっとできないんですよ。しかもこのときはその先に待っている大変な苦難、困難を知らないので……。
逃げ場を作らずギリギリの状態で掴んだ「グラミー賞受賞」への道

やっぱり根拠のない自信による、しかも宣言しちゃったことに伴わない行動はかっこ悪いじゃないですか。だからすごく危険なことを言ってしまうと、2年前グラミー賞を受賞できなかったら、もしかしたら今みたいに笑顔で人と会えるような自分はいないかもしれません。
本来はノミネートさえほぼ無理な話で、「なんて大きな賭けをしてしまったんだろう」と今でも胸がつかえるので「もし受賞できなかったら」という想像はできないですが。
それでも音楽を続けるのか、それともほかのことをするのか、でも今からなにができるんだろう、とすごく考えました。「死に物狂い」っていう言葉の意味はこういうことなんだなっていうのを実感するくらい、「無理だったらこうしよう」というのが考えられない状況でしたね。
逃げ場がない状況ですね。
本当に全員が認めてくれるような偉業っていうのは、逃げ場を作っていないから成し遂げられるのかもしれません。でもその分、精神状態が危険でもあると思います。
僕、偉人の格言が好きなんですけど、昔は「あなたがすごいからそんなことを言えるんでしょう?」って思っていたのに、今は「偉人もみんな最初はすごい人ではなかったんだな」って感じます。一生懸命無謀な夢に向かって、その努力を超えた人だけが発せる言葉が格言なんだと。
グラミー賞に関しては、自分のようにひとりで成し遂げた日本人が、坂本龍一さん、喜多郎さんなど僕の中で5人いるんですよ。ということはすでにエビデンスがあるともいえるので、それが支えになりました。
ちょうどコロナ禍というのもあって、しかも4枚目のアルバム『Heritage』は命懸けで臨んで叶わなかったので、結構精神はギリギリの状態でした。
そのときに支えてくれた方やものなどはありますか?
やっぱり母ですかね。2024年の3月に亡くなってしまったんですけど、あまりにもその存在は大きくて、いつも「人と比べるな」とか「自分に勝ちなさい」って言ってくれていた言葉が支えになっていました。
そのとき彼女の体もあまりよくなかったので、急がないと!という気持ちもありました。ちゃんとグラミー賞というプレゼントができてよかったです。
考えてみれば、バンド時代は大阪出身なので「大阪城ホールでライブをする」というのが夢だったんですよ。それが途中で「グラミー賞受賞」に変わり、死に物狂いで臨んで、叶って……。
でも受賞して感じたのは、こんなにも名誉ある賞をいただけたのはもちろんうれしいことですけど、でもその過程でいろんな人に出会って、仲間ができるという思わぬご褒美もたくさんいただいたなと。
2度目のグラミー賞受賞のチャンス。今の心境は?

きたる2025年の第67回グラミー賞においてもソロシングル「Kashira」が最優秀グローバルミュージックパフォーマンス部門にノミネートされていますが、今の率直な心境を教えていただけますか?
毎回のことながら、ほかのノミニーがすごいんですよ。今回はジェイコブ・コリアーとかシーラ・Eとか。本当に全員すごいんですけど、そもそも受賞しない可能性のない人はそこにそもそもいないんですよね。
ノミネートされた以上は、だれが受賞するかわからないっていうところで、今は音楽を新たに作るよりも、プロモーション期間にしています。
チームのみんなで2年前と同じようにプロモーションして、恵比寿神社に参拝して、現地に行ってからも2年前に行ったお店と同じところで食事をしようっていう、願掛けです。ただひとつ違うのは母がいないので、「お母さん応援してね」って心の中で話しかけています。
きっとどこかから見てくれていますね。
そうだといいな。あと前回はソロ名義だったんですけど、今回はフィーチャリングアーティストが3人、ニューヨークとロサンゼルスとカナダにいるんです。
彼らは前作も一緒に作っていたメンバーなんですが、今回は正式なノミニーということで、2年前よりも孤独を感じないというか、励まされている気持ちでいます。
『ドラクエ(ドラゴンクエスト)』ではひとりで戦ったけど、『ドラクエⅢ』では仲間が増えて4人で戦う、みたいな(笑)。みんなで一緒に同じ夢を見られるのはわくわくしますね。
この2か月くらいしか味わえないので、この時期にメディアで取り上げていただけるのはすごくうれしいです。世間的には受賞するかどうかという点に注目しているというのは理解しているんですけど、自分が努力できるのはここまでなんですよ。
ノミネートできるかどうかが本当はとても重要なことで、このあと受賞できるかどうかはアウトオブコントロールなんですよね。自分の手を完全に離れてしまっているというか。だから僕としてはノミネートされた瞬間のほうが、努力が報われたという実感が大きいです。
「グラミー賞2025」を音楽家としてのひとつの区切りにする

受賞に向けたプロモーションというのはご自身で行われるんですか?
自分以上に自分のことを理解して宣伝できるプロモーターはいないと思います。最近はご自身でMVを制作される方もいますし、それに宣伝が加わるというイメージかもしれません。
でもクリエイティブなこととプロモーションって脳の使うところが全然違うので大変そうです。
そうなんですよね、だから切り替えがすごく大事です。僕はバンド時代もプレイヤーというよりもプロデューサーに近い目線で活動していたというのもあり、わりとそういうことができるほうの音楽家だと思うんですけど、でも全部英語でやらなきゃいけないし、切り替えスイッチは多いですね。
ただAIの台頭もありますし、音楽業界の衰退が著しいと感じていて、このままいくと悲惨なことになりかねないと思っています。全部を自分で行う時代が、もしかしたらもう来ているのかもしれないと。
アメリカはやっぱりそういうのをキャッチするのが早いので、アーティストがファッションブランドを作ったり、香水を作ったりしてマネタイズするという動きも始まっていますよね。
でも日本で同じことをすると「あいつはミュージシャンじゃなくなった」って言われたりするんです。やっぱりアーティストがビジネスについて考えることを美徳としない文化があるんですよね。
僕もバンド活動をしていたころ、「お金のことは考えるな」って言われました。まぁその意図は人それぞれで、「だから音楽に集中していいんだよ」という意味でおっしゃった方もいたと思いますけど。
でも今の時代、全体の分母が著しく減少しているのに、そんな考え方を続けていたらやっていけないと思うので、僕は次の一手を考えているところです。
音楽以外の一手ということですか?
音楽業界にはいるつもりですけど、今度のグラミー賞が発表されるタイミングで区切りをつけて、プレイヤーとして専念するというのは終わりにしようかなと思っているんです。
たとえば育てる側に回るとか、プラットフォームを作るとか、今いろいろと想像しているところなんですけど。
音楽だけでやっていける時代ではなくなったといいますか、もちろんたとえばミリオンアーティストとかはやっていけると思うんですけど。ってもう「ミリオン」も売れないので「ハンドレッドサウザンアーティスト」ですかね(笑)?
まぁとにかく、これからはアーティストがそれぞれどうやって生き延びるかを考える時代が来るんじゃないかと思います。
時流には逆らわず、逆手にとる

音楽業界を低迷させたのはストリーミングサービスだとおっしゃる方もいますが、どう思われますか?
それも一端として考えられますが、でもストリーミングサービスが広まったことで得られたこともあるんですよね。僕の「Spotify Wrapped(#Spotifyまとめ)」を見ると、100以上の国で聞かれているんですよ。それってCDを買うしかなかった時代には絶対にありえなかったことだし、すごいことですよね。
とはいえサブスク反対派のアーティストにもさまざまな理由があると思いますし、まぁ「音質」という点なら納得ではあります。
今、こんなに気軽にネット上で音楽を聴けるようになったのに、ヴァイナル(レコード)やカセットがまた伸びてきていて、音楽を大切に聴く、音質にお金を払う、そういう人も増えてきているので、二極化しているなと思います。
ストリーミングサービスについては、いつも家電に置き換えて考えるんですけど、たとえば昔の冷蔵庫って電化製品ではなく、中に氷を入れて使うアナログなものだったんですよ。
そのうち今の形になって、氷なんて必要なくなりました。このとき最初は電気で冷えるなんて半信半疑で否定する人もいたかもしれません。でもどんどん改良されていって、氷屋さんの仕事を犠牲に、一家に一台欠かせないものになりました。
その時流によって変わっていくすべてのテクノロジーは、都度最初は否定されるんだと思います。でもいずれ普及していく。だから残念ながら、それによって被害を被る人は絶対にいるんですよ。まぁまさか音楽家もそうなるとは、って感じではありますけど(笑)。
何事もどんどん波のスピードが早まっているので、時流には逆らわず、むしろ逆手に取って行動を起こしたほうがいいんじゃないかなと思います。

グラミー賞を受賞するために必要なことを学べるオンラインアカデミーを開講予定。
登録者は宅見さんによる授業を受けたり、オンラインで対談したりすることができます。また実際に作曲する様子を生配信で見られたり、月に1回の豪華ゲスト陣との対談、そして実際に直接話すことができるオフライン交流会にも参加可能。
ひとり異国に飛び立ち道を切り拓き、グラミー賞にも輝いた宅見さんの今までの軌跡を辿り、そのノウハウを知ることができるチャンス。とくに音楽業界を志す方は要チェックです!
詳細はこちらをご確認ください。