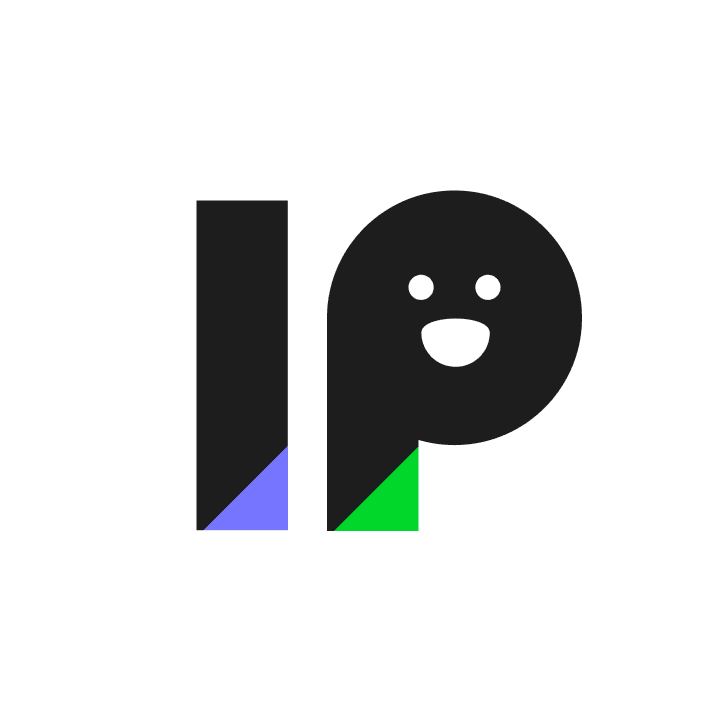東京生まれ、渋谷ラバー。2011年小説『空のつくりかた』刊行。その後アパレル企業のコピーライティングをしたり、webメディアを立ち上げたり。最近の悩みは、趣味が多すぎてなにも極められないこと。でもそんな自分が好きです。

内野聖陽×岡田将生『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』上田慎一郎監督の“戦い方”
低予算のインディーズ映画ながら異例の大ヒットとなった『カメラを止めるな!』(2017年)は当時、社会現象にもなりました。監督を務めたのは上田慎一郎氏。これほどまでに大きな印象を残す作品を作ってしまうと、その後の作品があまり評価されないという方も少なくないですが、上田監督の場合は違います。
続く劇場用長編作品『スペシャルアクターズ』は「ぴあ映画初日満足度ランキング」や映画レビューサイト「Filmarks」の満足度ランキングにおいて高い評価を得ており、さらには活躍の場を“横型動画”にとどめず、TikTokと第76回カンヌ国際映画祭による第2回「#TikTokShortFilm コンペティション」にて、監督を務めた『レンタル部下』がグランプリを受賞。
挑戦をおそれずに楽しみながら映像を制作する姿に、思わず「またなにかおもしろいことをやってくれるだろう」と期待を寄せる人も多いのではないでしょうか。
2024年11月22日(金)には、内野聖陽さん演じる税務職員と岡田将生さん演じる天才詐欺師が異色のタッグを組み、壮大な“税金徴収ミッション”に挑む痛快クライム・エンターテインメント『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』の公開を控える上田監督にインタビューをしてまいりました!
今作の制作秘話はもちろん、映画監督を目指すにいたった中学時代の話や作品づくりにおけるユニークなモチベーションなどいろいろとお聞きしたので、上田監督のファンのみならずクリエイターの方々にもご覧になってほしいです。
- 中学生のころから父のハンディカムで映画づくり
- 縦型動画・横型動画は水泳の自由形・平泳ぎのようなもの
- 最新作『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』は真面目な税務職員×天才詐欺師のケイパー映画
- 内野聖陽さん・岡田将生さんらキャスティングはサッカーチームをイメージ
- 「12時間ルール」を設けたうえでスクラップアンドビルドを繰り返す
- “後出しじゃんけん”はしない

中学生のころから父のハンディカムで映画づくり

早速ですが、映像制作を始めたきっかけについてお伺いできますか?
実家がめちゃくちゃ田舎で、映画館に行くのも電車で1時間くらいかけないといけないようなところで育ったんですが、レンタルビデオ店は1軒だけあったんですね。
それで小学生のころから映画を見るようになって、中学に入ってからは父のハンディカムを借りて、友だちと毎日のように放課後に撮影をして映画のようなものを作っていましたね。
そのころにはすでに映画監督になりたいと考えていたのでしょうか?
いえ、そのときは全然。ただ楽しくて撮っていたという感じですね。それで高校に入って、1年生のときから毎年文化祭のたびに映画を作ったんですよ。
文化祭って、だいたいどのクラスもおばけ屋敷とかたこ焼き屋さんとかやるじゃないですか。でも自分のクラスは「映画を作ろう!」と決まり、3年間毎年撮っていましたね。
3年生のときには120分の戦争アクション映画みたいなものを作って、それが地元の新聞に取り上げられたり、ホールで上映してくださったりしたんです。
好奇心旺盛なのでずっといろんなことをやっていたのですが、いつも映画や物語を作るっていう分野で一番褒められるなと気づいて、進路を決めるときに「映画監督っていう道もあるか」と目指しはじめました。
縦型動画・横型動画は水泳の自由形・平泳ぎのようなもの
劇場用以外にYouTubeやTikTok、VRなど媒体を絞らずに映像を制作されていますが、それぞれどのようにアウトプットの方法を切り替えているのでしょうか?
@picorelab "Rental Subordinates" #shortfilm #tiktokshortfilm #cannes2023 #grandwinner
♬ オリジナル楽曲 - 上田慎一郎 - 上田慎一郎
たとえばTikTokはスマホで見る方が多いと思うので、縦型のショート動画を作っているのですが、縦の画角って人間を収めるのにフィットしていて、なんとなく横型よりも身近に感じるんです。ライブ配信も横型より縦型のほうが親近感が沸きません?
縦型動画は登場人物に親近感を抱きやすくて、没入感も得やすいのかなと思いながら撮っています。映画館と違って、2時間じっくり座って見てくれるとは限らないので、横型動画よりもかなりテンポを上げていますね。
同じ競技の違う種目という感じです。たとえば「水泳」という競技は一緒でも、自由形と平泳ぎは種目が違いますよね。それに似ている気がします。
でも異なる種目で結果を出すことは難しいですよね。映像も同じように縦型と横型、それぞれ撮り分けるのはとても難しいのではないかと感じます。
でも実際に自由形と平泳ぎでメダルを獲得されている選手もいますし、たぶん種目によって泳ぎ方は変えていても、どこかつながるところはあるんじゃないかと思います。
映像も同じで、劇場用映画を作りながら気づいたことが縦型ショートを制作するときにも活かせるし、縦型ショートで得たことが映画にも活かせるというふうに、フィードバックし合えていると思うんです。
最新作『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』は真面目な税務職員×天才詐欺師のケイパー映画
最新監督作の『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』についてお伺いしたいのですが、邦画では今までありそうでなかったといいますか、かゆいところに手が届く作品だなという印象を受けました。
僕ハリウッド映画育ちなんですよ。『オーシャンズ11』シリーズのような、犯罪者たちがそれぞれの特技を活かして大金を強奪する、といったケイパーものがすごく好きで、日本映画でも作りたいと思っていたんですよね。
そのうえで、今作の主人公の熊沢は真面目な公務員です。いわばどこにでもいそうなおじさんが、オーシャンズ11のような世界に迷い込んでしまった、というようなリアルとファンタジーどちらも感じられる映画を目指しました。
真面目な税務職員と天才詐欺師という、一見交わらなそうなふたりが手を組んで脱税王から大金を騙し取るというストーリーなんですが、熊沢は真面目なので、やっぱりモラルは守りたいわけです。
モラルを守りながら詐欺を行いたい、凸凹コンビといいますか、ふたりの掛け合いも見どころかなと思います。
メインビジュアルのキャッチコピーがまさしく「モラルを守って 騙しましょう」ですもんね。

今作は韓国ドラマの『元カレは天才詐欺師~38師機動隊~』という作品が下敷きになっていますが、恋愛要素をなくしてバディものにしたり、かなりアレンジされた部分が大きいかなと感じます。どのように物語をふくらませていったのでしょう?
伊藤主税プロデューサーに「一緒に映画を作りませんか?」と声をかけていただいて、ドラマを見てみたらとてもおもしろかったんですよ。ただ日本ではたぶんラブコメ路線で押し出そうということで、こういったタイトルがつけられたんだと思いますが、原題(『38 사기동대』)はまったく違うんですよね。
たしかに恋愛要素はあるけども、僕自身「公務員と詐欺師のバディものだよな」という気持ちが強かったです。それで全16話のドラマを2時間の映画にするために、なにを削ぎ落としてなにを足すか考えて、バディもの、ケイパーものにしたうえで日本っぽさを加えています。
もともと熊沢の真面目な税務職員というキャラクターだったり、ことなかれ主義だったり、怒りという牙を抜かれてしまった大人という要素は、むしろ韓国人よりも日本人のほうがフィットするんじゃないかという気持ちもありました。
とくに原作ドラマでは、熊沢役にあたるソンイルという役をマ・ドンソクが演じているんです。正直ちょっと強そうじゃないですか(笑)。『アングリースクワッド』は、より「気弱な公務員」という要素を立てていますね。
内野聖陽さん・岡田将生さんらキャスティングはサッカーチームをイメージ

熊沢を演じたのは内野聖陽さんですが、まさしく「気弱な公務員」という印象が強くて、最初「えっ本当に内野さん?」と思ってしまいました。バディを組んだ天才詐欺師、氷室役の岡田将生さんもハマり役でしたが、キャスティングはどのように決められたのでしょうか?
一人ひとり決め方は違ったんですが、主演の内野さんについては僕から提案しました。彼が出演されていたNHKの『スローな武士にしてくれ〜京都 撮影所ラプソディー〜』というドラマがあり、そのなかで格好悪い男と格好いい男、どちらも素晴らしく演じていらっしゃったんですね。
それを見て「もう内野さんしかいない!」と思ってお願いしました。内野さんって本当に作品ごとに別人のように変わるじゃないですか。だから本当におっしゃるように「熊沢が内野さんって気づかなかった」とおっしゃる方もいるんですよね。
だからこそ、本当に実在している公務員に見えるんじゃないかなと思っています。この役はやっぱり「映画のような世界に迷い込んでしまった一般人」にしたかったので、自分でコントロールしてスターのオーラを消せる方にお願いできてよかったです。
岡田さんは、すぐに満場一致で決まりました。この氷室という役を日本で演じて一番ハマるのは岡田さんしかいないだろうと。
たしかにお似合いでしたね。ちょっとニヒルな表情にも、見る者にひと目で氷室という人間をわかりやすく伝えてくださる力を感じました。

氷室という人物は熊沢の味方ではあるんですが、ずっと危うさをはらんでいるんですよね。「なにか隠しているんじゃないか」「いつか手のひらを返すんじゃないか」という疑いを拭いきれない危うさを岡田さんがずっと纏ってくださっていて、素晴らしかったですね。
ほかにも川栄李奈さんや森川葵さん、真矢ミキさん、皆川猿時さん、小澤征悦さん……と挙げていたらキリがないほど豪華な俳優さんたちが出演されています。登場人物の多い作品ですが、みなさんだれ一人存在感が薄れることなく魅力を発揮されていて素敵でした。


ありがとうございます。原作ドラマのキャラクターの要素は残しつつ、しかし引きずられすぎないように、というバランスを考えながら、そのうえでこの映画ならではの新しい人物造形をしたいと考えてキャスティングしていきました。
サッカーチームを作る感じですかね。全体のバランスはとても大事なんですよね。フォワードだけ11人いても勝てないし、ゴールキーパーがいて、ディフェンスも司令塔も必要で……というのは映画も同じかなと思います。
もちろん一人ひとり「この人がいい!」という理由はありますが、そのうえで全体のバランスを見ながら強いチームを作っていったという感覚です。
税務職員側がいて、詐欺師がいて、橘(小澤征悦さん演じる脱税王)陣営がいて、全員に見せ場があって、その見せ場に必然性があって、それぞれのキャラクターが立っているというものを目指しました。
「12時間ルール」を設けたうえでスクラップアンドビルドを繰り返す
今作のプロジェクトは『カメラを止めるな!』(2017年)の公開前から動かれていたそうですが、制作中にコロナ禍を迎えるなど社会情勢にも大きな変化がありました。今まで制作されてきた作品とは異なる点で苦労されたことはありませんでしたか?
僕自身、こんなに大きな規模で、こんなに著名な俳優たちと一緒に長編映画を作るというのは初といっていいんですよね。ですので初めてのことが多くて、それが大変でもあり、楽しくもありました。
たとえば、僕は撮影前から俳優たちとコミュニケーションをしっかり取って、一緒に作品を作っていくというスタイルが多いんですが、スケジュールの都合もあるので名のある俳優たちと同じようにできるのかなと不安があったんです。
でもその点については、内野さんのほうから「撮影前からがっつり肩を組んで一緒にやっていきたい」と言ってくださったので、本当に脚本段階から何回も一緒に打ち合わせを重ねて作ることができました。
あとリハーサルはチームごとに何度も行いましたね。熊沢家だったり、税務署員だったり、詐欺師メンバーだったり、橘陣営だったり……。そこはすごくよかったところです。
ただみなさんやっぱり歴戦の猛者ばかりじゃないですか。ですので現場でたくさんアイデアが出るんですよ。今までも俳優の方からいろんなアイデアをいただくということはありましたが、比較的自分が決めていくことが多かったと思います。
でも今回は「こっちのほうがおもしろいんじゃないか」「いや、こっちのほうがいい」という意見がどんどん出てくるんです。それ自体はすごくうれしいことなんですが、短い時間でその中からひとつを決断しなきゃいけないというタフさがありました。
最初のプランを壊したほうがおもしろいけど、そうすることでほかの場面まで壊れないか、それならどう変えればいいか、というのを常に瞬時に判断しなきゃいけないし、作品を再構築する必要性も出てきます。
とくに今作は伏線やトリックが重要なエンターテインメント作品なので、現場で変更を繰り返すというのは難しそうな感じがするんですが、でも最後まで流動的にみんなで作っていきましたね。それがとても刺激的でした。
スクラップアンドビルドですね……お話を聞いているだけでも大変そうです。
でもそういう現場だったからこそ、そこで生まれたライブ感や熱みたいなものが映ってくれているんじゃないかなと思っています。
たしかに拝見しながら覚えた躍動感はそういうところに起因しているのかもしれないです。

上田さんは撮影中にコロナに罹患してリモート演出をされたそうですが、そんなにも臨機応変に動かなくてはいけない現場だとなおさら苦労されたのではないでしょうか?
大変でしたね(笑)。コロナになったのは撮影中盤だったんですが、その日から自宅待機になり、でも制作スケジュール的に止めることはできなかったので、隔離期間は自宅からリモートディレクションを決行しました。
食卓にiPadをふたつ並べて、そこに現場のモニターを遠隔で飛ばしてもらって、現場には「天の声」みたいに自分の声が届くスピーカーを置いてもらって……。
大変だったんですが、気づきもあったんですよね。僕、普段現場で走り回りすぎちゃうタイプなんです。
でも落ち着いて俯瞰で見ざるをえない状況になって、現場を走り回って渦中にいると見えなかったものがあったんだと気づきました。ですのでそのリモートディレクションを経験して以降は、以前ほど走り回らなくなったんですよ(笑)。
お話をお聞きしていると、その場その場の状況に柔軟に応じる方なんだなと感じます。前作『ポプラン』(2022年)の制作時には労働基準をしっかり設けて撮影されたそうですが、それも環境をよくしていこうという思いによるものだったのでしょうか?
実は労働基準については今作制作時にも行ったんですよ。
え!この豪華キャストで可能だったんですね?
そうなんです、このメンバーでこの規模だと難しいんじゃないかといわれていたんですが、実施できたんです。
「12時間ルール」という、1日の撮影時間は基本的に最長12時間、そのうえで撮影終了から次の撮影開始まで10時間のインターバルを設けるということを決めて撮影しました。
どうしても12時間を超えてしまうという日もあったんですが、そういうときもちゃんと現場の皆さまの了承を得ないと延長できないと定めましたね。
もちろん労働環境をよくしたいという思いもあるんですが、個々のパフォーマンスを上げるという目的もあるんです。
たとえば深夜2,3時まで撮影をして、次の撮影が早朝時集合だったら数時間しか寝られないですよね。未だにそんな現場があるかどうかはわからないですが、ひと昔前はあったと思うんです。
そうするとやっぱりパフォーマンスがガクッと落ちるんですよ。撮影は1日で終わるものじゃないので、最長12時間まで、さらに10時間空けるって決めておけば、翌日もその翌日も高いパフォーマンスで臨めるじゃないですか。
個々のパフォーマンスが上がれば作品のパフォーマンス力も上がるので、そのためにもしっかり休む時間を確保するほうがいいんじゃないかと思っています。
“後出しじゃんけん”はしない

上田さんの作品というと、今作ふくめどの作品にもユーモアがあると思うのですが、そういった「おかしみ」にアプローチするために普段から意識されていることなどはありますか?
たぶん性分だと思います(笑)。ウェットな場面、シリアスな場面があまり書けない(笑)。もちろん書こうと思えば書けるんですが、筆がそっちに向かないといいますか……。湿っぽいのがあまり得意じゃなくて、やっぱりコメディが好きなんですよね。
笑いって見る者が予期していることから外れたときに生まれるものなんじゃないかと感じるのですが、常に新しいアイデアを生み出すのは大変ではないですか?
基本的には「お客さんに負けないぞ」と思っています。ある意味戦いなのかもしれません(笑)。
やっぱり見に来てくれたお客さんの期待を下回ることはできないじゃないですか。だから見たことがあるものはできるだけ避けようとしています。
あと今作の場合、お客さんと僕で読み合いになると思うんですよね。「こう来るだろう」「お約束的にはこうだからこうしよう」みたいな。期待を超えたいというモチベーションは常に持っていますね。
まさか「戦い」という言葉が飛び出すとは予期していませんでしたが、とてもおもしろい表現です。
あまりよくない言葉かもしれないですね(笑)。楽しませたいという気持ちです。でもそういう意味では、お客さんも負けたいと思って見に来てくれていると思うんです。
はい、負けたいです(笑)!
そうですよね!僕もいち映画ファンとして「全部読めたなー」「勝ってしもたー」っていうふうに思ってしまう作品は避けたいし、真剣勝負で作っていかないといけないと思っています。
ただ難しいのは、今作のような作品の場合、フェアにヒントも出さないといけないんですよ。じゃないと後出しじゃんけんになってしまうし、それではお客さんは納得してくれません。
だから伏線もヒントも出しながらフェアに勝利をしないといけない。大変なんですが、でもそれを考えるのがすごく楽しいです。
2024年11月22日(金)新宿ピカデリーほか全国公開
配給:NAKACHIKA PICTURES JR西日本コミュニケーションズ