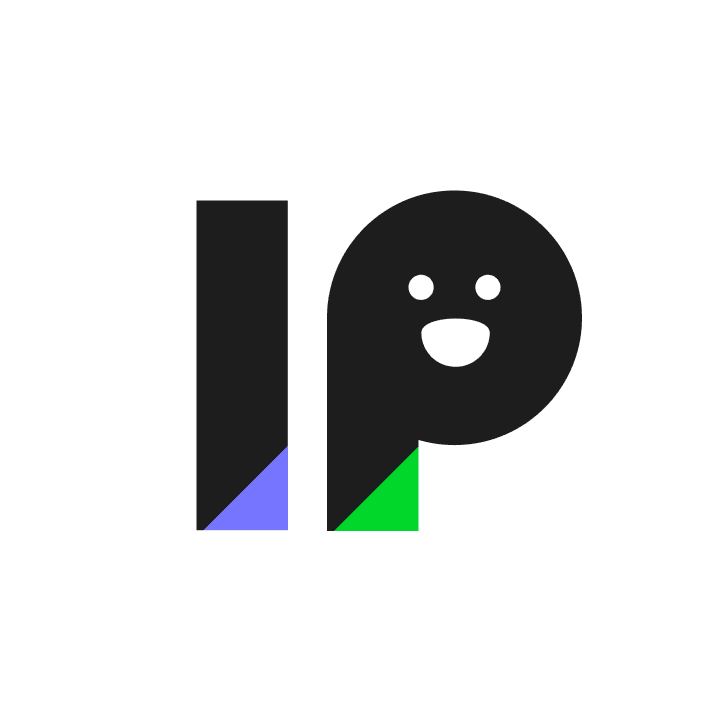
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。

「自作プログラムの著作権はどこまで保護されるの?」「他人のプログラムを改変して使いたいけれど、どこまで許される?」
プログラムの著作権について、上記のような疑問を抱えている方は少なくないでしょう。プログラムの著作物は著作権法によって保護されますが、保護対象かどうか判別するのは容易ではありません。
本記事では、プログラムの著作権がどこまで保護されるのか、安全に他のプログラムを利用するポイントや実際の判例を解説します。
プログラムの著作権について理解を深めたい方、開発の際に注意が必要な点を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

プログラムが著作物だと認められる場合は、著作権保護の対象です。
著作権法で保護されるのは「著作物」のみです。著作権法第2条第1項第1号で定義される「著作物」とは、思想や感情を表現した創作性があるものを指しています。
プログラムで創作性があると判断されやすい箇所は以下です。
著作権法10条3項1号では、プログラムを作成する手段となるプログラム言語や規約、解法は保護対象ではないと定められています。規約はインターフェースやプロトコル、解法はアルゴリズムなどを指しますが、「プログラムを組むために使うもの」に著作権は認められません。
一般財団法人ソフトウェア情報センターSOFTICが公表したデータによると、昭和62年度から令和6年度までに登録されたプログラムの著作物は、合計12,982件です。
参照:e-Gov 法令検索「著作権法」
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作物って何?」
参照:一般財団法人ソフトウェア情報センター「プログラム著作物の登録申請状況」
なお、著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

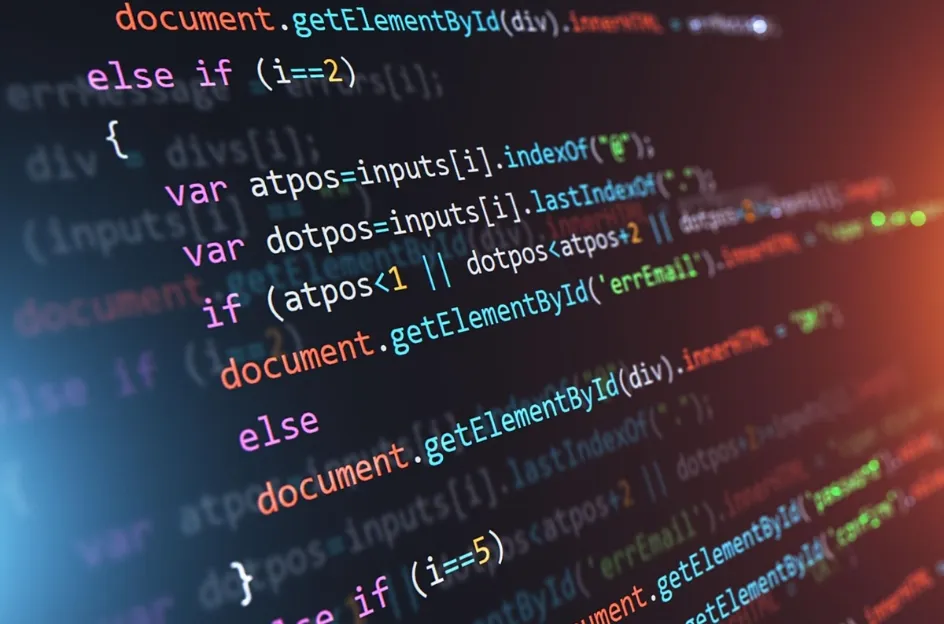
著作権法第2条第1項第10号の2において、プログラムとはコンピュータを使ってある結果を得られる指令を組み合わせて表現したものとされています。
著作権法第10条1項9号では、「プログラムの著作物」は著作権法で例示される著作物に該当し、保護対象になりえると明記されています。
作成者が記述した指示に従って一つの結果を得るものがプログラムであるため、アプリケーションプログラムやシステム、ソースコードやルーチンも著作物に該当するのが特徴です。
ただし、著作権法で規定する「プログラム」に該当しても、すべてが著作権で保護されるわけではありません。
また、プログラミング言語やアルゴリズムなどは法律上「プログラム」ではない点に注意が必要です。
参照:e-Gov 法令検索「著作権法」

プログラムの著作権の帰属先は、原則として作成者です。しかし、職務著作である場合は法人に権利が帰属するため、帰属先の扱いに注意しましょう。
「職務著作」とは、作成者が雇用主などの指示を受けて作成することを指します。著作権法第15条2項では、規定の要件を満たすプログラムは職務著作だと定めています。
具体的には、作成するプログラムが、法人からの依頼によって契約する者が職務上作成するものである必要があります。同時に、法人等の名義で公表され、法人等と従業員間で特別な取り決めがないことも要件です。
これらに当てはまるプログラムの著作権の帰属先は、作成者ではなく作成を依頼した法人等になります。
なお、法人等と作成者が雇用契約を交わしていない場合の扱いは異なるため注意しましょう。業務委託契約などでプログラムを作成した場合、受託者が著作者となるのが原則です。
業務委託契約などで依頼者が受託者から著作権を譲渡してほしい場合は、権利の譲渡に関する契約を交わす必要があります。
参照:e-Gov 法令検索「著作権法」
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作者にはどんな権利がある?」

プログラムの著作権に関する3つの判例を紹介します。
プログラムの著作権譲渡が義務かどうか争われた判例を紹介します。これは、契約書を作成せずにソフトウェア開発をした結果、著作権の移転が認められなかった判例です。
発端は、出版社がテスト問題を自動作成するソフトウェア開発をベンダーに委託したことにあります。委託の際、正式な契約書は作成されていません。
その後ベンダーが廃業したため、出版社はソースコードの提供を要求しました。しかしベンダーは提供を拒否し、出版社側は引渡義務違反だとして訴訟に至りました。
平成26年6月12日に大阪地方裁判所で開かれた裁判の結果、出版社側の訴えは棄却されています。棄却の理由は、契約書がなく権利の譲渡に関する条文がないことや著作物の譲渡に合意した証拠がないことでした。
委託して作成されたプログラムの著作権は、受託者にあります。契約書で具体的な取り決めを交わしていないために、著作権譲渡が認められなかった判例です。
参照:裁判所 - Courts in Japan「裁判例結果詳細」
著作物の要件である創作性の有無が争われた判例に、「システムサイエンス事件」があり ます。
これは、プログラムのコードやルーチンに創作性は認められないとして著作権侵害が認められなかった判例です。
ソフトウェア開発会社のシステムサイエンス株式会社が、バイオテクノロジー関連の装置に関わるプログラムを4件開発しました。そのうち3件を複製、うち1件を翻案したとして、同業他社を著作権侵害で訴えたのが裁判のきっかけです。
裁判の争点は4件のプログラムに創作性があるかどうかでした。平成元年6月20日、東京高等裁判所は4件中3件の複製が著作権侵害だと認めています。
ただし一般的な組み方がある以上、普遍的なプログラムは類似するものです。またプログラムの処理の流れ自体は「解法」であり、保護の対象外であることが判決を左右しました。
参照:一般財団法人ソフトウェア情報センター「SLN SOFTIC LAW NEWS No.14」
参照:日本ユニ著作権センター「判例全文・1989/06/20」
ソフトの操作画面が似ているとして著作権侵害を訴えたものの、訴えが棄却された判例を紹介します。
サイボウズ株式会社は、ネオジャパン株式会社が自社ソフトを複製しているとして、類似ソフトの頒布と使用許諾の差し止めを求めました。
平成13年6月13日の仮処分申立事件の裁判では、プログラムの創作性が認められ、一部ソフトの使用許諾を禁止する仮処分命令が出されています。
しかし、ネオジャパンは仮処分決定後も使用許諾を続けたため、サイボウズが訴訟するに至ったのです。
東京地方裁判所は2002年9月5日の判決で、複製や翻案は認められないとしてサイボウズの訴えを棄却しました。両者のプログラムは操作性に類似点はあるものの、プログラム間の画面全体の印象は共通していないとしたのが棄却の理由です。
なお、サイボウズはネオジャパンとの和解成立を2003年5月30日に公式サイトで報告しています。
参照:大日本印刷株式会社「サイボウズ事件」
参照:ITmedia「News:「著作権侵害は行われていない」――東京地裁、サイボウズの主張を棄却」
参照:サイボウズ株式会社「株式会社ネオジャパン社に対する 差止請求控訴事件の和解成立のご報告」

プログラムを法的に保護する方法は以下の2つです。
コンピュータプログラムは、プログラムの著作物として著作権の登録申請が可能です。
著作物は創作された時点で著作権が発生するため、登録は原則不要とされています。しかし、プログラムの法的安全性を確保するため、著作権者の登録が可能です。
現在の日本における著作権保護期間は「著作者の死後70年間」です。保護期間を明らかにするために、権利の発生年月日を明らかにする必要があります。
絵や音楽のように公開日が判別できる創作物は、保護期間が客観的に判断しやすいものですが、一方、プログラムは多くの場合、作成日が公開されません。著作権の発生日が不明瞭であるため、創作年月日の登録によって保護期間を明確にするのです。
プログラムの著作権登録申請は、文化庁が指定する登録機関で受け付けています。昭和62年から指定されている登録機関は、一般財団法人ソフトウェア情報センターSOFTICで、登録手数料は1件47,100円です。
参照:公益社団法人著作権情報センター CRIC「著作権は永遠に保護されるの?」
参照:一般財団法人ソフトウェア情報センターSOFTIC「プログラム著作物登録」
参照:文化庁「著作権登録制度」
プログラムが「発明」にあたる場合は、特許を取得することで権利の保護が可能です。
特許を取得する際は、特許庁へ申請します。申請が認められると、プログラムを出願した日から20年間、プログラムの保護が可能です。
特許を取得すると、特許の取得者が独占的に使用できるようになると、特許法第68条で定められています。
特許が認められるのは「発明」に限られ、普遍的なものは認められません。プログラムにおいては、独自のアルゴリズムや新機能などの「アイデア」に該当するものが特許を取得できる可能性があるでしょう。
特許権が認められるためには、審査に合格する必要があります。申請したプログラムがすべてが認められるわけでない点に注意が必要です。
参照:特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは」
参照:e-Gov 法令検索「特許法」
参照:弁理士法人ライトハウス国際特許事務所「ソフトウェア特許の保護範囲とプログラムの著作権」
なお、特許についてはこちらの記事で詳しく解説しています。


プログラムの著作権を侵害しないための注意点は以下の3点です。
プログラムの著作権を侵害しないため、著作権の帰属先や譲渡のタイミングなどを細かく決めておくことが重要です。
まずは、開発者と依頼主の関係を明確にしておきましょう。開発者と依頼主の関係によって著作権の帰属先が変わるためです。
たとえば開発者が企業に雇用されている場合、プログラムは職務著作にあたるため、企業が著作権者になります。
一方、開発者が業務委託契約等によってプログラムを作成した場合、著作権者は開発者となるのが原則です。
企業が開発費用を支払ったからといって、著作権が依頼主に帰属するわけではない点に注意しましょう。著作権の譲渡を求める場合は、契約書で譲渡に関する条約を取り決める必要があります。
参照:Authense法律事務所「プログラムは著作物にあたる?著作権法の対象?知的財産権について弁護士が解説」
参照:クレア法律事務所「プログラム等従業員が創作した著作物の著作権の帰属」
トラブルを未然に防ぐため、書面で著作権の取り扱い方を決めることが重要です。
プログラムの著作権は、原則として作成者本人に帰属します。作成を依頼した側は、著作権者になりません。
プログラムの著作権を移転する場合は著作権の取り扱い方を契約書に明記すると、著作権侵害を未然に防げます。
契約内容は以下の項目などを明記するとよいでしょう。
著作権の移転をする場合、著作権法第27条および第28条の権利も対象だと明記するとすべての権利を移転できます。著作権法第27条は翻案権、第28条は二次的著作物としての利用権を認める条文です。
仮に契約書で著作権を移転する取り決めを交わしても、それだけでは翻案権と二次的著作物利用権は譲渡されません。
翻案権と二次的著作物利用権が譲渡されないと、プログラムの修正や修正後のプログラムの使用ができないため注意が必要です。
参照:e-Gov 法令検索「著作権法」
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作者にはどんな権利がある?」
プログラムの著作物の取り扱いは複雑なため、弁護士のサポートを受けるのも有効です。プログラムは創作性の有無を判断しにくく、著作権侵害しているかどうかの法的判断が難しいのが特徴です。
まったく同じプログラムでも、作者の個性が認められなければ著作権侵害にあたりません。
また、プログラムは一般的に公開されていません。非公開のプログラムは入手しにくく権利侵害しているか判別しにくいです。そのため、目的が同じプログラムは意図せず類似する可能性が高いといえます。
このようにプログラムの著作物は取り扱いが特殊であり、正確な理解は困難でしょう。
プログラムの著作権の取り扱いは、実際の運用状況や契約内容によって判断が変わります。そのため必要に応じて、専門知識と経験のある弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。
参照:IT企業・インターネットビジネスの法律相談「プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説」
参照:企業法務の法律相談サービス「著作権について弁護士に相談して解決する必要性と弁護士費用の目安」

プログラムは著作物だと判断された場合に著作権が認められます。
原則として開発者に権利が帰属しますが、職務著作の場合は法人等が権利者になるため注意が必要です。プログラムの著作権者として権利を保護する際は、指定の登録機関に著作権の登録申請をしましょう。
著作権の権利を侵害しないためには、詳細な契約内容の記載や、専門知識のある弁護士への相談が重要です。
トラブルを未然に防ぐことを心がけ、プログラムを安全に活用しましょう。
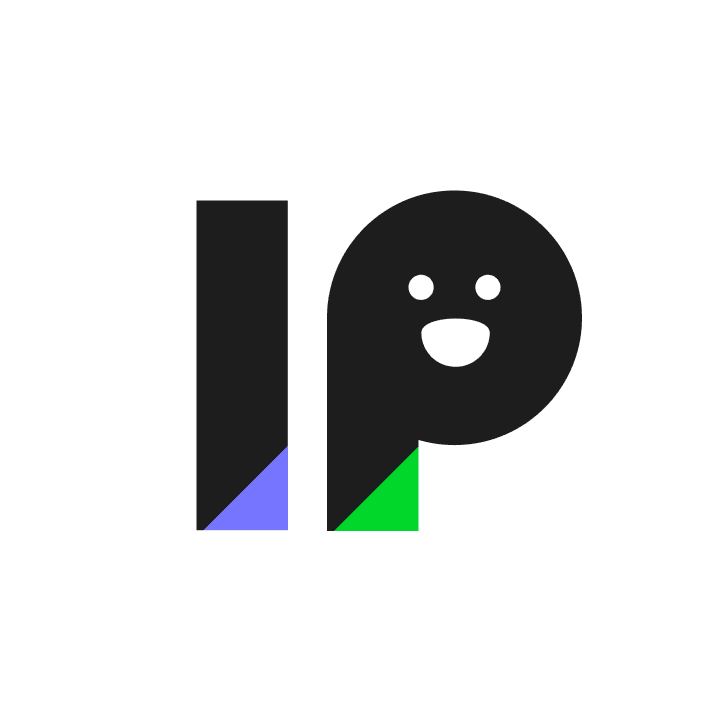
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。