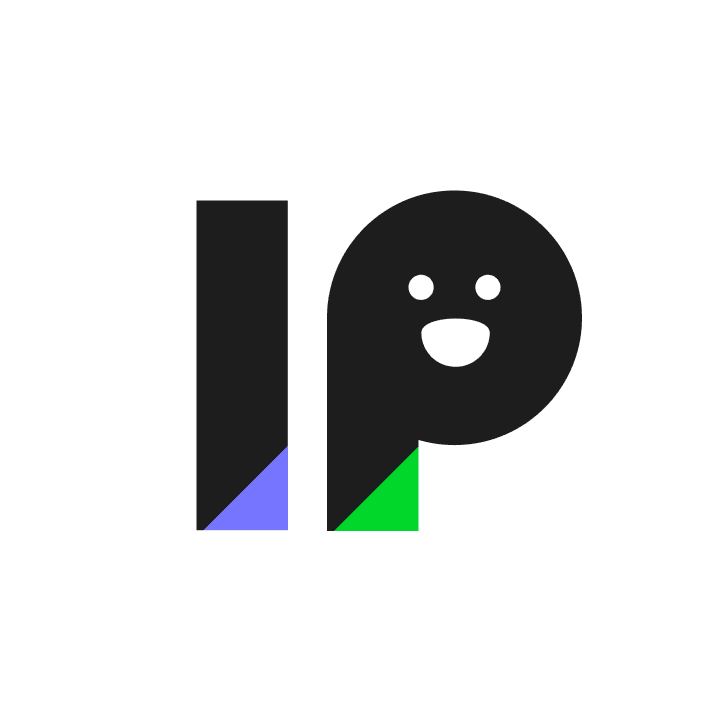東京生まれ、渋谷ラバー。2011年小説『空のつくりかた』刊行。その後アパレル企業のコピーライティングをしたり、webメディアを立ち上げたり。最近の悩みは、趣味が多すぎてなにも極められないこと。でもそんな自分が好きです。

映画監督 枝優花さんが“だれでも映画を撮れる”映像飽和時代に思うこと
2017年クチコミなどを中心に広まり、上映館拡大、そしてロングラン大ヒットとなった映画『少女邂逅』(主演:穂志もえかさん、モトーラ世理奈さん)。監督・脚本を手がけたのは当時弱冠23歳の枝優花さんです。
実はご自身の14歳のころの実体験が原案になっているそうで、瑞々しくも切なさとはかなさ、そして痛みさえ覚えてしまうほどの鮮烈さに心を奪われた者も多く、今もなお彼女の手がける多くの作品には少なからず繊細な揺らぎを感じます。
映画だけでなく『ワンルームエンジェル』や『瓜を破る〜一線を越えた、その先には』といった連続ドラマ、マカロニえんぴつや羊文学などのミュージックビデオと幅広く映像作品を制作。
最新作であるanoの「愛してる、なんてね。」のミュージックビデオ/Unplugged Short Movieも話題です。また写真家としての活動も活発で、ドラマ『スメルズ ライク グリーン スピリット』のキービジュアルも担当。
初の長編作品がヒットしてから7年、今や彼女をロールモデルとして映像業界を目指す若者も多いですが、そんな次世代を担う者たちに伝えたいこと、そして現在の映像制作の現場に思うことなど、深いところまでお聞きしました。
- 人前で自分を使って表現することに喜びを感じなかった
- いかに作っている人間に「当事者性」があるか
- SNSでだれとでもやりとりしやすくなった時代の弊害
- 作品は人間が作っている
- 女性もヤクザものを撮りたいしカーチェイスだって撮りたい
- 「だれでも映像を撮れる時代」だけでいいんだっけ?
- 人は嘘がないものを見たいわけじゃない、いっぱいの嘘の中にひとつだけ本物があればいい
- 「こっちからの発信」だけでは自分が広がっていかない

人前で自分を使って表現することに喜びを感じなかった
早速ですが、クリエイティブ活動を行うきっかけになったこと、映画監督を目指すきっかけになったことはありますか?
もともと映画監督を目指していたわけではないんですよね。でも子どものころ、家の都合もあって近所の友だちと同じ保育園、学校に通っていなかったので、わりとひとりで過ごすことが多くて、自然と映画を見る機会は多かったです。
みんなが思い描くような「保育園の先生になる」とか「パン屋さんになりたい」といったイメージもなかったし、なんとなく漠然とスクリーンの向こう側に触れてみたいとは思っていましたね。
幼少期は俳優のワークショップを受けられたこともあるんですよね?
映像業界って入りたいと思っても、入り方がよくわからないじゃないですか。しかも具体的にどういう仕事があるのかもわかりにくいし、私も現場なのか配給なのか、やってみないことにはなにをしたいのかわからなかったので、そこに近づくなにかとっかかりが欲しかったんだと思います。
実際にワークショップを受けてみていかがでしたか?
そのとき小学5年生くらいだったんですけど、「楽しい」と思えるまではいかなかったんですよね。このときにそう思えていたら役者も向いていたかもしれないです。
結構頭で考えちゃうタイプなので、体を動かして、人となにかをして楽しいっていうのは感覚的に思えないところがあって、でも「違うな」って思えたのも、それはそれでいい気づきでした。
人前で自分を使って表現することにあまり喜びを感じなかったというか、それによって自分という人間の尊厳が満たされるという感覚がまったくなくて、むしろ身を削ってしんどいなって思ってしまったんです。
俳優って実際はどうあれ、きらびやかで華やかに見える人気の職業なので、自分が合わないんだってわかったときの若干の寂しさというか「そっかー、自分は表に立つタイプじゃないのかもなー」という妙な納得感はありましたね(笑)。
だからこそ今、一緒に仕事をするうえで俳優たちにリスペクトを持っているっていう部分もあります。
いかに作っている人間に「当事者性」があるか

作品を制作するまでいろんな工程があると思うんですが、一番好きな部分を挙げるとしたらどういったところですか?
自分でも現場に入るたびに「どの部分が好きなんだろう?」って考えることもあるんですけど、身も蓋もないことを言ってしまうと、結局全部好きなんですよね……。
映像を作るときの工程を大きく分けると3〜4つくらいになるんですけど、「準備」、それから「現場」、「仕上げ」、放送・公開中の「宣伝」に分けても、全部全然違っていて、そのうえで全部おもしろいです、関わる人も全部違うし。たぶん最初から最後までいるのって私とプロデューサーくらい。
準備の段階についてお話しすると、たとえば脚本の打ち合わせのなかで、話し合っていくうちにみんな自分ごととして考えていくようになるので、原作があってもオリジナルであっても楽しいです。
主人公の話をしているはずが、いつの間にか自分の話になっていたり、それで「あれ?これって俺たちの話だ」って気づく瞬間があるんですよ。
作品を作るうえで大事なのは、いかに作っている側に当事者性があるかどうかだと思っています。だから作品の根幹となる人間が「これは自分たちの作品だ」って自覚できる瞬間がとても楽しいと感じます。
たとえば「原作が売れているから」「ヒットしているシリーズだから」「自分はあんまりわかんないけど、若い子たちに刺さっているから」くらいの船の乗り方だと詰めの甘さが出てしまう。なので企画の段階でどれだけ自分ごととして語れるかを大事にしています。
制作の過程で、スタッフみんなの当事者性がだんだん詰まっていく、それがすごく好きなんですよね。
現場が始まるとさらに人数が増えて、文化祭前日状態になります。文化祭は一向にやってこないのに、ずっとその準備をしている状態というか。
ライブと違ってお客さんの反応は作品ができあがってからしか見えないので、我々は自分たちの作っているものを信じて、ただ作り上げるしかなくて、それがいいチームだとやっぱり楽しいです。
漫画だと映像よりも奇跡が起きにくいというか、たとえば晴れのシーンをイメージしているなら晴れにできるので、描き手の演出ですべて決まります。でもその分そのジャッジに責任が伴います。
映像は良くも悪くも私以外の力がめちゃくちゃ働くので、晴れのシーンの予定だったのに雨が降ったり、想定と違う展開になることが多くて、でも結果的にそれがいい画になることもあるので、少しだけ無責任になれるんですよね。
昔は「欲しかった画が撮れない」とやきもきしたこともあったんですけど、今はわりと偶発的なものに乗る楽しさがあります。「やれることを全力でやってみよう」と思えるし、それを一緒に楽しめるチームだと「結果的によかった」って思えます。
連ドラや映画を作るとなると、本当に長い間一緒にいることになるので、家族みたいになっていくし、それもめちゃめちゃ楽しいんですよね。
一方で仕上げの段階になると、急に人数が減って私と編集さんの2人になり、この空気も好きです。現場は外交的で、大人数で作業をすることが好きな人が多くて、仕上げの人たちは黙々と作業するのが好きな人が多い印象があります。私自身はどちらも好きなので、両方味わえてラッキーです。
とくに編集作業は、すでにある素材をもとにどういいものを作っていくかの勝負であり、現場とは違う魔法をかける時間。切り貼りによってまったく違うものになる楽しさがあり、プロの手を借りて冷静に判断できるので、すごく好きです。
SNSでだれとでもやりとりしやすくなった時代の弊害

宣伝の段階になったら、とにかく見てくださった方の反応を見ます。結構勉強になることも多くて、社会の流れも見えてくるので次の作品に活かせるんですよね。
「ここに反応するんだ!」とか「自分たちはここがポイントだと思っていたけど、こっちなんだ!」とか。とくに連ドラは数か月かけてムードが変化していくので、作品が視聴者によって育つおもしろさがあります。
そういった視聴者の意見をもとにその後の展開や演出を変えることもありますか?
そういう作品もあるかもしれないんですけど、私の場合は全話撮りきり放送の作品しかしたくない‥‥もうつらすぎて(笑)。
単純にいろんな反応を見て揺さぶられながら作るのは疲れてしまうし、準備が間に合わないなかの追いかけっこは避けたいし、あとそもそも結末が決まっていない状態で演出をすることに結構抵抗があります。
見てくれている方の反応が盛り上がっていれば、もちろん現場にもいい作用がありますけど、批判的な場合は食らいますよね、やっぱりみんなSNSで反応を見ているので。
なので基本的には見すぎないようにしています。ドラマ放送直後にハッシュタグをつけてつぶやいてくれている方たちの意見は見ます。それはたぶん、その作品を見たくて見てくれている人たちだから、受け止めたいなと思うんです。
一方で作品を見ずに、一部を切り取った動画や予告だけを見て意見する人や情報をきちんと確認せずに勘違いしたままの人もいますよね。規模が大きくなればなるほど混沌としていく。それで疲れてしまって、宣伝しか投稿できないと思うこともあります。
作品は人間が作っている
日本の映像業界は男性が多く、年齢層も高いですが、枝さんは大学時代から映画を作りはじめ、初の長編作品公開は23歳のときですよね。なにか大変だったことなどはありますか?
20代前半のころはいろいろありました。当時は「映画と認めないぞ」とか「映画とはどういうものなのか教えてやろう」と言われたり、初めて映画を公開したときはそれで疲弊することもありました。
ただ「監督」という仕事の役割があれば、なにを言われてもそんなに気にならないようになりましたね。
自分自身の人格と役割そのものを切り離すのは難しいと感じる人も多いような気がします。
私の場合は、自分を尊重してくれる人が増えてきたのが大きいかもしれないです。前は「若いから」とか「ちょっと話題になっているから」などの外側だけを見てオファーされることも多い印象でした。
だから条件も厳しいものが多くて、でもそれは「最初に受ける洗礼」なんだろうなと思って向き合っていました。最近はそれも変わってきて、仲間が増えたり、ちゃんと過去の仕事を見て頼んでくださったり、というのがちょっとずつ増えてきて現場も楽になりました。
働いている量とか仕事の数とかはたぶん20代から変わっていないんですけど、今の方が断然楽です。やっぱり自分に対してのリスペクトが増えたことで、負担が減ったことが大きいのかなと思います。

ただ最近はテレビという媒体で作品を作るようになって、より多くの方が見てくれることで考えることも増えました。そこから、あえて作り手として顔を出すようにしています。
SNSの影響もあってかなり混沌とした意見が飛び交う世界になってしまったといいますか、それが直接、その対象となる本人の視界に入るような状況になっていますよね。軽く発信できるようになった世の中だからこそ、言葉一つひとつが実は重みを増しているんじゃないかと思います。
とくに矢面に立つ役者がそれを一身に受ける状況にも疑問があります。だって彼らを演出して世に届けているのは、監督やプロデューサー、スタッフたちなので。
けれど意外とテレビを見ている側はその認識が薄い。作品が自分と同じ人間が制作しているという感覚が欠落している。これだけ簡単に言葉が届く世界になってしまった今だからこそ、「自分と同じ人間が作っている」ということを知ることは、ある程度必要なのではないかと思います。
女性もヤクザものを撮りたいしカーチェイスだって撮りたい
女性の映像業界への参入も増えてきたと感じますが、まだ苦労することやギャップを感じることも多いとお聞きします。
私の場合はたぶんもう慣れすぎてしまって苦労とも捉えていないんだろうなと思うんですけど、それでもありますね。たぶん9割くらいは男性だし、準備……ロケハンとか打ち合わせとかをする段階はほぼ100%男性です。
現場に入ると女性のヘアメイクさんやスタイリストさんも加わって少し緩和されますけど、それでもやっぱり私が直接腹を割って話す相手は男性ばかりです。
「ふと気づいたら男性しかいないな」ってこともあるなかで、本当に細かいんですけど、食事がしんどいかもしれません(笑)。お弁当を出前するにもジャンクなものが多く……。

私は体質的にどうしても油が分解できないからラーメンが苦手で、もちろんみんなもそれを尊重してくれるんですけど、すごく食べたそうにしながら「でもだめなんだよね……」と言わせてしまったり。女性が多いチームだと野菜が食べられるので感激します(笑)。
正直肌が荒れたり、爪がボロボロになったりするだけでもテンション下がるし、日焼けもしたくない。たまに「なんでこんなふうになってまでやっているんだろう」という気持ちになるのを女性がいれば話せますよね。話せるだけでいいんです。「早くシャワー浴びたいよね」とか、共感し合えるだけでストレスは軽減します。
でもいま一緒に仕事をしている組は女性が多くて、ロケハンのときもカメラマン以外全員女性というときがあって、帰りがけにそのカメラマンに「全然悪いことはなにひとつないんだけど、今日1日ちょっとそわそわした。枝ちゃんはいつもこういう感じなんだね」って言われました。
男女の人数が逆転することもあるんですね!業界全体としても変化が起きはじめているところなのでしょうか?
変化はしていますが、まだまだ表層的な部分が多い印象ですね。たとえば「インティマシーコーディネーターを入れましょう」と決まっても、なぜ入れるのか根本的なところを理解できていない。「とりあえず入れておこう」という感覚ではせっかく環境を整えても、結局現場でだれかを傷つける発言や行動をしかねないですよね。
ちょっと話が変わりますが、表面上の「女性らしさ」ばかり大事にされすぎるのも違うかなと思います。私は女性ですが、ノワールやカーチェイスも撮りたいし、オカルトも好きです。
ありがたいし嬉しいというのは大前提として「繊細な女性同士の……」と謳う作品をお願いされることが多く、カーチェイスや銃撃戦の激しい作品のオファーは来ないです。実際、女性監督がそれを担うことは少ないと思います。でもそれも「イメージ」ですよね。
その一方で男性は、女性が主人公の恋愛ものを撮ることもある。だから女性も1回ヤクザものを撮っちゃえば「こういうのもできるんだ」っていう認識に変わると思いますが、なかなかまだ機会に恵まれていないです。
韓国の『ヴィンチェンツォ』という、イタリアンマフィアの顧問弁護士が悪徳弁護士と協力して韓国で壮絶な戦いを繰り広げるドラマがあるんですけど、それを監督しているのはキム・ヒウォンという女性なんですよね。
韓国映像業界も長らく男性社会が続いていたなか、この作品がヒットしたことで、この方がパイオニアとして「女性の監督もこういう作品を撮れるんだ」と認知されはじめ、ちょっとずつ変わってきているっていうのを韓国の映像業界の方から聞きました。
そういった流れが日本でも広まればいいなと思います。男性だからこういう作品、女性だからこういう作品、という考えに対しては「そんなに雑に括ってしまうのもったいなくないですか?」と。
属性でその人のキャラクターが決まるわけじゃないですもんね。
そうなんです。女性の監督だからって繊細で人を傷つけないとは限らないし、私よりも繊細な男性監督もいます。だからその一人ひとりの本質に見合った仕事ができるようになるといいなーと思いますね。
「だれでも映像を撮れる時代」だけでいいんだっけ?
IP magは若年層の読者も多いので、もしかしたらこれから映像業界を目指す方も読んでくださるかもしれないと思っているんですが、そういった方々に向けてなにかアドバイスなどはありますか?
ここ2,3年くらいはずっと「だれでも映像を撮れる時代」っていうフレーズをよく聞くようになったと感じます。
実際ネットに自作の動画を上げている子は多いし、スマホやカメラの性能が発達して敷居が下がり、だれでもチャレンジできるようになったのは本当にいいことだと思います。
でも、こんなにも映像飽和時代になって「『だれでも作れる』でいいんだっけ?」とも思います。「だれでもできる」がいい一方で「自分にしかできない」も大事だと思うんです。
自分にしか撮れないもの、自分だからこそできることが掴めないと、結局この業界に入ってきてもすぐ辞めたくなると思います。出入りの激しい業界なので、私は簡単に「みんな入ってきてよ」とは言えないです。

隠さず言えば、簡単に入るにはあまりにもしんどすぎる、コスパが悪すぎる(笑)。現場はとくに、ある程度「まぁいっか!」と楽観的に流せる能力がないと大変だと思います。真面目にしっかり考えるタイプだったら、こんなに大変な仕事は選ばないんじゃないかな(笑)。
映像業界にかぎらず、どんな仕事でもそうだと思うんですけど、「これは私にしかできないな」「私だからできたんだ」って思える体験の積み重ねが、その仕事を続けられる一番の要因になると思っています。そういう体験を増やすには「なぜ自分はそれを作りたいのか」っていう部分に興味がないと難しいですよね。
「だれでも映像を撮れる時代」という言葉は危うくて、ヒットクリエイターを見て「私もああなりたい」って思うのはもちろんいいけど、それはあくまでもきっかけでしかなくて、入ってからもずっと「何者かになりたい」というだけではもたない業界です。実際に入って、作って、そのうえで自分とどれだけ向き合えるかが大事だと感じているんです。
とくに監督は本当にやることが多い。脚本作業や演出をするうえで、ある程度社会のことを知っておかないといけないし、現場においてたくさんの人を動かすためのコミュニケーション能力も必要だし、映像や音楽、美術の知識もないと構成、演出はできないし……。
私自身も光が当たっている部分を見せているので、若い子から「どうやったらなれますか?」とたくさんメッセージをいただきますが、実際のところ「バットを100回振って1回当たればいい」という感覚なんですよね。
普段から「100回振っています!」とわざわざ言う必要もないので見せていませんが、99回もへましているなかで、当たった1本だけがメディアに出ているという感じ。だから現実を目の当たりにして「え、こんなこともしなくちゃいけないの?」「こんなに地味なの?」「なんか思ってたのと違った」って辞めていっちゃう子が多いんですよね。
入るハードルが下がったのはもちろんいいけれど、本質的な部分をだれも伝えていないなーと。「その後の保障をしないなら、なんのためにだれでも参加できるようにしているんだっけ?」とも思います。
「この仕事、私にぴったりだ!」と感じるには、その「ぴったり」の感覚が自分にとってどういうものなのかを知る必要があります。苦しいことが多いほうがぴったりと感じる人もいれば、楽しく安心して働くことがぴったりと感じる人もいる。要は、自分がどういった人間なのかを知る作業が大事で、それがわからないかぎり、どこへ行っても「なんか違う」と感じる気がします。
だから少し重いことを言ってしまいますが、映像業界に来るなら、苦しいことも傷つくことも楽しいと思えるような力をつけてほしいとは思います。最初はつらくても、1年後なのか3年後なのか、必ず回収されます。
たまに現場でしんどそうにしている子がいるんですよ。死にそうな顔でスタンドインしていて、「3日後には辞めちゃうかも」と思って呼び出して話を聞くと「自分が役に立っていない気がして、意味がない存在だと感じてつらいです」と。
そこで「意味はあるよ」なんて甘い言葉をかけても仕方がないので「最初の現場での自分なんてほぼ意味ないから!」って言っちゃうんですが(笑)。
けど実際、自分では「たいしたことのない仕事」と思っているかもしれないその積み重ねで現場は動いていて、自分が準備したものが役者のいい表情を引き出すひとつになっていたり、現場の空気作りのひとつを担っていたり、お客さんの心を動かすものになっている、と少しずつ実感を得ることが大事。本当に大切なことって、実は地味で小さいし時間もかかる。
これって映像業界にかぎらず、どの仕事も同じだと思うんです。どんなに大きな有名企業に入っても、結局自分の存在価値は自分で見つけださないと。どこに行ってもそのことに気づけなければ同じ。
「価値」なんて言葉を使いましたが、私は自分にそこまで価値があると思っていないです。なので雑に扱われてもあまり傷つかずに「まあそうですよねー!頑張りますー!」くらいで流してきまして……それはそれでどうなんだと思いますが(笑)。
「自分は大事な存在」と思うことはもちろん大事。でもいい意味で「自分はたいしたことないんだ」と思うことも、ある程度は必要なのかなと。自分ひとりではたいしたことがないからこそ、だれかがいるし、わざわざ一緒に生きているのだと思うので。
人は嘘がないものを見たいわけじゃない、いっぱいの嘘の中にひとつだけ本物があればいい
大人になるにつれてそういう部分に蓋をして自ら鈍感になる道を選び、後悔はしていないものの「それでいいのかな」と思っていたときにあの作品と出合って、もしかしたら枝さんは心の柔らかい部分をそのまま持ちつづけて大人になったのかなと感じたんですけど、自分らしさをどう保つかというのは意識されていますか?
ありがとうございます(笑)。私の場合は、周りに恵まれているんですよね。
その柔らかい部分ってもともとはだれしも持っているじゃないですか。大人になってもそれがなくなったわけではなくて、心の奥底には残っている。でも表に出すとつらいから底に沈めていって鈍感になっていくのが処世術というか。
「裏切られたからもう簡単に人は信じないぞ」とか「ある程度諦めていく」とか、自分もある程度プライベートではやっていると思うんですけど、でも人に恵まれているので、自分のあまりにもピュアすぎる部分やすぐ人を信じちゃうところをないがしろにされない環境で生きられています。
こちらが優しく生きていても同じくらい優しい人がいて、たとえ傷ついたとしてもそれを再確認し合える仲間が増えてきました。そういう仲間が少なかったころは、もっと尖っていたような気がします。
大人になるにはふたつの方法があると思っています。ひとつはそのピュアなものを持ったまま丸くなれるパターン、もうひとつはそれを沈めて丸くなるパターン。
ものづくりをする身として、後者になってしまうとマズイと感じています。とはいえ意識するのはすごく難しい。
映像を作っていると、自分の思いどおりにならないことのほうが多いです。さまざまな都合で「納得してください」と言われてしまうこともある。納得いかないながらもそのことに慣れてきている自分もいるので「そうだね、みんな立場があるから大変だよね」と納得することも増えました。
20代前半のころとは違って、そこで怒ってもなにもならないというのも理解し、自分でも大人になったなと冷静に感じます。でもこの間、仕事の合間、炎天下の坂道をのぼっているときに「なんで私だけこんなに物分かり良くないといけないの?」って突然イライラが募ってきて、「やっぱりこれはたぶん1回キレとかないとだめだ」って感じて、友だちに連絡しました(笑)。
なにを言っても落ち着いて聞いてくれる友だちがいて、その人に「ちょっと聞いてよ」と。もちろん「今こういう状況なのでキレさせてください」って前置きをしたうえで一気にメッセージを送って。
『少女邂逅』がなぜ当時たくさんの若い子たちに観ていただけたかって、たぶん私がめちゃくちゃ当事者だったからだと思うんです。もし私が「みんなのために作ります」という立場で作っていたら、たぶん見てくれた方は上から言われている印象を受けるだろうなと。
なので、いま私はこんなにブチギレたい当事者なのに、なんで「自分の気持ちはさておき」という気持ちで進行しているんだ、と思いまして。まだ「むかつく」までは達していないんだけど、1回ちゃんと怒っておかないとやばいっていう感覚になって、友だちには申し訳ないですが力を借りました。

そしたらその友だちもずっと私を見てきた人なので「嫌だろうけどあんたは結局戦場に行って、ボロボロになって『つらかったです』って言いながらなにかを掴む、みたいなことをしないとだめだよ」って返されました。
「大人になったら丸くなって縁側でゆっくり休みながら戦場を眺めるみたいなたしなみ方もあると思うけど、あんたは無理だと思うよ」と。たしかにそうなりたかった自分もいるんですけど、でもそうなったら自分がつまんなくなるんじゃないかという怖さもあるんですよね。
もちろんずっと10代のころのままでいろとは思わないです。それは無理だし、もうそこで戦う体力もない。だからこそ今の私ができるやり方で戦う方法があると思っています。
人はべつに嘘がないものを見たいわけではなくて、嘘がいっぱいあってもその中に一個でも本物があればついてくるのかなと。「嘘がない」という誠実性に向き合いすぎて自分の汚い部分とか、どうしようもない、だれにも見せたくない本物の部分がなくなったら、おしまいかなと。
だからこそアンコントロールな部分は飼いならさないよう整えずに放置して、常に自分が動物でいても大丈夫なように、自分自身に振り回されるということも意図してやっていく、というのは必要かなと思います。もう『少女邂逅』のときほどの危うい感覚はないですが、でもまだまだその先の自分のままならない部分もあるので。
たぶん監督をすること、というか、なにかをクリエイトするってこういうことだと思うんです。一生自分と向き合うっていうことを楽しめる人だったら、いくらでもやっていけると思うし超楽しいと思います。
でもやっぱり本来はそこまで向き合わなくていいんです。大人になって、とくにたとえば家族ができて子どもが生まれたら、自分の人生ばかりに集中することもできなくなるので。
クリエイターはいつまでも自分が主人公でないといけない苦しさを抱えているので、それが楽しめる人だったらどんどんこの業界に飛び込んでほしいですね。
「こっちからの発信」だけでは自分が広がっていかない
これから先、新たにやっていきたいことはありますか?
もちろん映像は引き続き作っていきたいし、やりたい作品もいっぱいあるんですけど、そういうのは知り合いのプロデューサーとかに「こういうのやりたい」と話しているので置いておきますね。

今は映像の仕事につながるかどうかわからないものに興味があります。「仕事ばっかり」っていうのもきついし、結果的に仕事につながればハッピーとも思いますが。
実は私自身はフィクションよりドキュメンタリーを見るのがすごく好きなんです、自分がわかりえない世界を見せてくれるので。
なかでも食に興味があるので、世界中の食べ物とかレストランのドキュメンタリーを見ることが好きで、私自身が撮りたいわけではないんですけど、そういうカルチャーに関われたらいいなと思っています。
そこで学んだものを自分の作品にフィードバックできると思うんですよね。なので外の世界に気持ちが向いています。
「こういう作品を作るためにここに取材に行こう」というふうになってしまうと、得るものの範囲が狭まるので、プライベートで触れていきたいです。仕事のためだと必要な分しか集めないし、自分自身が全然広がらないと感じて。
だから自分が興味あるなと感じたことはちょっとでもいいからどんどん触れていきたいですね。突発的に海外に行ったり……っていうのは、だんだん「スケジュール的に難しい」などと腰が重くなっているので自戒として言っています(笑)。
口に出していかないとどんどん簡略化、効率化していこうとして、「今じゃなくていいか!」と年を越すということが多いので、もっと衝動的に、読んでいた本に影響されて「ここ行きたい!」って行ってしまうぐらいの自分になりたい!という感じです(笑)。
いいですね!そういうのを経て、またさらに作品の奥行きが深まっていくのかなと思うと、いちファンとしてなんだかうれしいです。