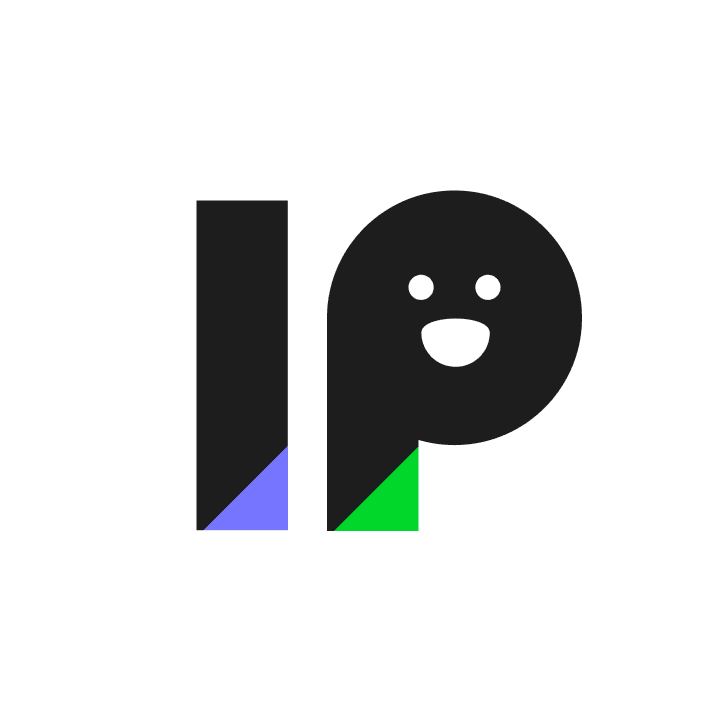東京生まれ、渋谷ラバー。2011年小説『空のつくりかた』刊行。その後アパレル企業のコピーライティングをしたり、webメディアを立ち上げたり。最近の悩みは、趣味が多すぎてなにも極められないこと。でもそんな自分が好きです。

ダウンタウンDXの名物プロデューサー西田二郎氏が語る“天才”の証明【後編】
『ダウンタウンDX』の名物プロデューサー西田二郎さんへのインタビュー後編。当記事では、テレビ業界が今後生き延びるための西田さん流の考え方や、3.11、コロナ禍といった未曾有の事態の影響などについてお話しいただいています。
- 大阪・東京・名古屋それぞれの土壌に合った番組づくり
- 第2、第3の自分を生み出すために
- テレビ業界はもっとつまらない番組を作ったほうがいい
- 3.11をきっかけに生まれ変わり、現在は“若手”の感覚
- 南極に降る雪は誇りを抱いている

大阪・東京・名古屋それぞれの土壌に合った番組づくり

讀賣テレビは近畿広域を放送対象としていますが、西田さんは全国区の番組も制作されていますよね。エリアごとに番組づくりの違いなどはありますか?
まず東京と関西の違いについては、スタッフの人数も、リサーチの仕方も、情報の取り方も全然違うので、完成した番組にも大きな違いが出ていると思います。一番注目してほしいのは名古屋と関西のクリエイティブの違いですかね。
関西に関しては、スタッフも演者さんと同じ空気を吸って、一緒になって場を作っていくという文化が根づいています。だから事前に演者さんに渡す情報は少なめ。
一方で、名古屋は関西を背中にして東京を向いている印象があります。多くのタレントさんを東京から呼んでいますし、明快なロジックと明快なストーリーコンセプトのもと作られるんです。
『携帯リレー』放送後、中京テレビ内でバラエティ番組を作る際の参考として試写会をしてくれていたみたいで、それがきっかけで中京テレビやそのグループ会社のCTV MID ENJIN(ミッドエンジン、コンテンツ制作会社)とつながりがあるんですが、中京テレビは基本的な素養だけでなく、それを活かせる体力、脚力が半端ないと思っています。クリエイティブの要はそういう“地肩”なんですよね。
演者さんにすべて頼るわけでもなく、しっかりベースを作ったうえに演者さんがいるというようなかたちで、大阪とも東京ともまたちょっと違うんですよ。たとえばいま放送している『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(中京テレビ制作、2021年〜)は名古屋クリエイティブの魅力が花開いたいい例だと思いますね。
IPができあがるには“場”が必要だと思うんです。名古屋という場があったから『オモウマい店』ができたと思うし、関西という場があったから『ダウンタウンDX』ができたと。逆に東京ではそういった番組はできなかったと思うし、でもやっぱり『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ制作、2007年〜)は関西や名古屋では作られなかったと感じますね。
僕自身は早い段階で東京に来たんですけど、だからって「東京の人やねん」なんて思うことなく、大阪のテレビ局でやってきたことをベースに考えることが多かったので、それはよかったなと思っています。
ご自身のルーツを誇りに思っていらっしゃるということですか?
誇りもあるかもしれないですけど、やっぱり自分以外のだれかのもの、だれかの場所から自分のIPは生み出せないんですよ。真似するにしても、それを自分のものとしてどれだけ落とし込めるかが重要だと考えています。
「今の時代はこういうのが流行っているから」と分析するのも大事ですけど、そもそも自分たちがどんな文化で育ってきたのかを一切考えずに、人のやり方だけを移植しても、やっぱり自分のものじゃないから当たらないです。
ヒットする企画って、やっぱり自分の分身なんじゃないでしょうか。もちろんそうではなく当たる企画を作れる人もいるかもしれません。でも自分というものを突き詰めていれば、それがオリジナリティーになるし、それこそがIPになると思うんです。
第2、第3の自分を生み出すために

「未来のテレビを考える会」という社団法人を立ち上げ、次世代の教育やエンタメ業界の今後に向けて、さまざまな活動をされていますが、どのような経緯で発足することになったのでしょう?
もともとは『ガリゲル』(讀賣テレビ制作、2010年〜2019年)を制作していたころに、どんどん試写会などを実施して広めていきたいと企画していたら、日本テレビのプロデューサーが『水曜どうでしょう』(北海道テレビ制作、レギュラー放送は1996年〜2002年)のチーフディレクター 藤やん(藤村忠寿さん)と話してみたら?と提案してくれて、会ってみたのがはじまりでした。
いろいろ話をしていくなかで、テレビ番組を作るにあたっていろんな方がいろんな判断をしていかなきゃいけないから、作り手がどこまで魂を持ってやりきれるか、特にローカル局は難しい、そういうのを一緒に守っていったり、培っていけたらいいよね、と。
今から10年くらい前なんですけど、テレビ業界に対してふたりとも先行きの不透明さに不安を感じていたんですよね。「それなら、同じように感じている人たちを募ってなにかやろうか」とスタートさせたのがきっかけです。
現在はどのような活動をされていますか?
今は中央大学や神戸の流通科学大学などで、毎回いろんな方にゲスト講師に来ていただいて「プロデュース論」っていう講義をしながら、エンタメ業界をもっと身近に、とっつきやすいものだと感じてもらうための活動をしています。
あとは全国のいろんなローカル局の人とも対話を重ねて、現状の課題などをヒアリングしながら、「こういうことできるんじゃないか」と提案したり、実際にみんなでやってみたり、という感じですね。
テレビ業界を志望する方が減ってきているとお聞きしますが、実際に活躍している方のお話を聞けたら、就職先として選択肢にもあがりやすくなりそうな気がします。
僕自身、大学時代にテレビ業界に対してよくないイメージを抱いていたのに、実際に面接に行ってみたら「この会社いいな」とガラッと変わったくらいなので、もしかしたら同じように僕がケラケラ笑いながらテレビのことを話しているのを見て「なんかいいかも」と思ってくれる学生もいるかもしれないなと。
僕が大学でしゃべっているときの顔って、やっぱり讀賣テレビの面接で出会った先輩のイメージなんです。先輩に会って、全然テレビ局に行く気のなかった僕が入社したことを考えたら、時代が変わっても今もそんな学生がいるんじゃないでしょうか。
そんな第2、第3の西田二郎がいてくれたら、また「入社するつもりのなかったテレビ局に入って、結果すごく楽しい」っていう人間が増えるかもしれないですよね。テレビ局って自分なりのIPを作りやすい場所だと思うので、まずは作ってみて、それから辞めてもいいですし。
YouTubeやサブスク動画サービスの台頭で「テレビはもう終わり」って言う人もいますが、逆にいえば今までみたいに熾烈な争いをせずに自分の作りたいものを伝えやすくなったとも考えられます。
本来なら自分が作りたいものをテレビで伝えることができたかもしれないのに、世の中全体として「テレビは終わっています」というムードを受け入れちゃうんですか?と思うんですよね。
テレビ業界はもっとつまらない番組を作ったほうがいい

やっぱり、他人のことなんて考えずに自分が「おもろい」って思える番組をどんどん作っていったほうがいいですね。『携帯リレー』なんてまさしくそうで、深夜にたまたまテレビをつけた人が「なにやってんねん」って思いながらも、なんとなくそのまま見続けていたら、作り手の思いが伝わって結果、感動してたくさんのFAXを送ってくれました。
「時間を経てなにかを伝えられる」という観点においては、テレビが一番強いメディアなんじゃないかと思います。映画館やNetflix、Amazon Prime Video、そういったものは、自分で足を運んでお金を払って見に行ったり、大抵、特定のなにかを見ようとして開くじゃないですか。
そういう能動的に見るものではなくて、なんとなく見てしまって、そのまま引き込まれてしまうというのがテレビの本質なんじゃないでしょうか。だから、これからテレビはどんどん間違えましょう。どんどんつまらないものを作りましょう。
NetflixもAmazon Prime Videoも、めっちゃおもろいものばっかり作ります。それならテレビは「おもろいもん合戦」から離れて、おもろくないコンテンツを作っていく、それがこれから生きる道なんじゃないかと僕は思っています。
最近だと『VIVANT』(TBS系、2023年放送のドラマ)がめっちゃおもしろくてずっと見ていたんですけど、もしかしたら1回くらいあほみたいにおもろくない回を作ってもよかったかもしれません。「おもろくない」っていう言い方もよくないかもしれないですね、ずっと洞窟から出てこない、なにも進展しない回みたいな……。
あれだけ完成されたドラマなので、たぶん視聴率も下がらないですよ。みんな「きっとなにかある」と思って最後まで見て、ネット上で「この回なんや!?」と大騒ぎになり、その後「あの回見た?」と交わされるような伝説の回みたいになると思います。
……こんな勝手なことを言ったら、TBSさんや福澤さん(『VIVANT』の原作、演出を務めた福澤克雄さん)からお叱りを受けるかもしれないですけど(笑)、でもテレビの中であれだけすごいチャレンジをされた『VIVANT』という作品に対する愛があるから言っているんですよ。「今後のテレビってこうちゃうか?」っていう新たな提案を見せていただいたと思っています。
西田さんからまさか他局の番組のお話を聞けると思っていませんでした(笑)。
放送後なので宣伝にもならないですし(笑)。それでいうと、テレビ番組は基本的に1回きりという文化なので、それもまた残念な側面もありますが、1回の放送の中でなにをどう伝えるか、それが重要になってくるんですよね。
とはいえ『VIVANT』のような2回、3回見たほうがより深みが伝わるものもあるので、これからのテレビを考えるうえでは、かたちを変えていく必要があるのかというのも議論にあがってくるかもしれませんね。
3.11をきっかけに生まれ変わり、現在は“若手”の感覚

書籍を出版されたり、ラジオ番組のパーソナリティーを務めたり、テレビ以外の活動も多いですが、「IPを作る」という観点で一番成功したと思うことはなんですか?
「テレビの人間がこんなこともできるんやね」っていう表現はできたかもしれないですけど、ビジネスとして成功したとは思っていないんですよ。自分の持つIPをベースに、どんな新しいIPが作れるか、ずっとテレビ番組を作りながらもがいてきたという感じですね。
コロナ禍をきっかけに、もっと自分らしいIPがあってもいいじゃないかと思いはじめました。すべてが止まって、みんながあれだけ苦しい、大変な思いをしているときに、そりゃ笑えないですよね。
そういうときに「大丈夫や!みんな元気出していこうぜ!」って言える人もいて、それに勇気づけられる人もいると思いますけど、僕はそれはできない人間なんだと気づきました。
焦って無理に行動するのは、自分ではないことをすることになるので、自分自身が潰れてしまう。そう思って、ほかの人がいろいろと動いてくれていることに最大級の賛辞とリスペクトを送りながら、本当になにも自分からは発せられませんでした。電池切れみたいな……。
なにもできないことに申し訳なさを感じつつ、自分であるためにはどうしなきゃいけないのか見つめつづけ、そのうち街が元気を取り戻しはじめてようやく「こっちに行こう!」って声を上げられるようになり、人それぞれ与えられた役割があるんだなと感じました。
西田さんの人生で電池が切れたのは、はじめてのことでしたか?
3.11のときにもなりましたね。あのときは電池が切れただけでじゃなくて、自分自身がなくなっちゃいました。クリエイティブの水瓶みたいなのがあるとしたら、それがパッカーン!と割れたようなイメージです。水が全部流れていって、カラカラになったんですよね。
でも、自分がなくなったことを認めてしまったらこの仕事を辞めざるをえなくなるので、それは余計にみんなに迷惑をかけてしまうし、無理に自分は“ある”と嘘をついて過ごしていました。そのときが一番しんどかったですね。でもそのうち水瓶が修復されて、自然と水も沸いてきたんです。
当時すでに20年以上こういう仕事をしていたので、水瓶の水も、いわゆる継ぎ足しのコテコテになっていたと思うんですけど、一度すべてなくなって新鮮な水が入ってきたので、僕、そこからまたこの業界の1年生になったんです。
一度リセットされて、発想源などは変わりましたか?
発想そのものというより、発想の仕方が変わったという感じですね。それまでは、やっぱり自分の経験から「これってこうだよね」と読めてしまうことが多かったのが、いきいきしながら「うわ、また出た!」と楽しめるというか……。
もう30年以上この仕事をしていますが、感覚的には13年目くらいのディレクターと同じ。だから18年目、20年目の、本来は後輩にあたる“先輩”を見て、若手目線で「そんな予想どおりの企画でええんか?」と思うこともあります(笑)。
当然被災した方々のことを思うと「よかった」なんて絶対に言えないですし、二度と起こってほしくないですけど。でもやっぱり「いつでも笑っているキャラクター」っていうのが自分のIPなのかなと思いますね。
南極に降る雪は誇りを抱いている

IPは今後特にどういった媒体で必要とされると思いますか?
実は「媒体」というより、自治体の運営など、エンタメとは少し離れた分野のほうがIPという意識が大事になっていくかもしれませんね。
地方創生に注目が集まっていますが、大切なのはその地域のIPだと思うんですよね。観光資源や売り物ばかりでなく、そのIPにどう関わっていくかということがビジネスや移住などに影響してくるのではないでしょうか。現時点では「コンテンツ」と呼ばれていないそういった分野が、コンテンツ化される世の中になってくると思うので。
たとえば日本っていう国のIPはあるの?ないの?それをどう伝えるの?って考えたとき、日本のIPってアニメでしょうか?それだけじゃないですよね。じゃあ着物はどうでしょうか?……と、広げていくと議論できそうですよね。
これは僕の個人的な意見ですけど、南極ってIPがある気がしませんか?南極に降っている雪はもう「南極や!」って言っている気がしますもん(笑)。
やっぱりIPって誇りじゃないですか?「南極に降っている」という誇りがIPというものを認識させるんじゃないかと思うので、自分がなにを誇りに社会と接しているのか、その意識がIPを生み出すんじゃないですかね。
このときに重要なのは、まずは天才性をもってIPをスタートさせることだと思っています。その先に誇りがついてきて、IPになると思うので。
雪だったら「ええ雪できたでー」っていうところ。それが「南極に降ってるで〜うれしい〜」っていう誇りを生んでIPになるというイメージです。実際に南極の雪がIPに当てはまるかどうかという話は置いておいて(笑)。
常に自分で生み出したもの、あるいは自分自身を「ええ雪やで〜」と思えるかどうか、それがIPを生み出すうえで大切だと思います。
(もう一度前編を読む)