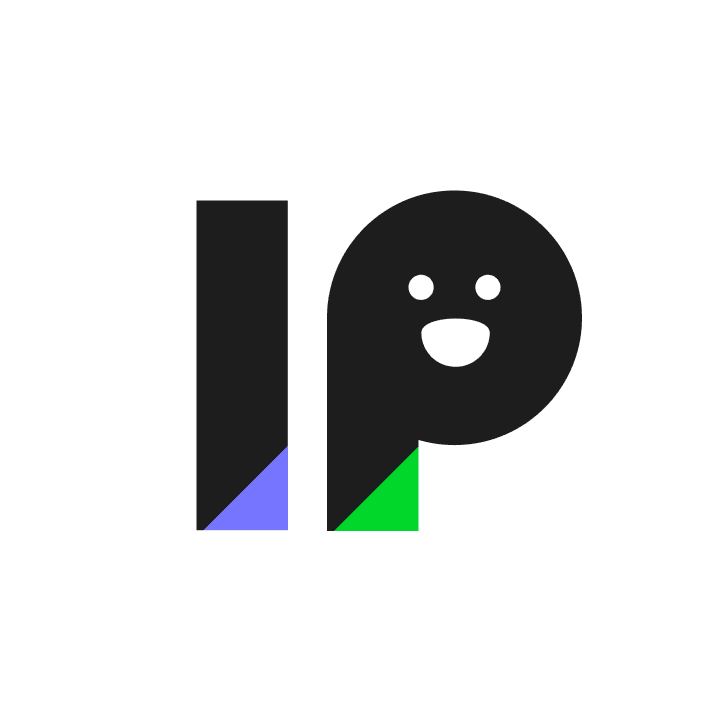
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。

「著作権マークの使い方や書き方がわからない」「著作権マークを勝手につけてもよい?」といった疑問をお持ちではありませんか。
著作権マークの表記にはさまざまなルールがあり、国によっても異なります。また、著作権に関連する他のマークとの使い分けも理解しなければなりません。
著作権マークを適切に使用しなかった場合、コンテンツの著作権が保護されない可能性もあるため注意が必要です。
本記事では著作権マークの書き方とその必要性、関連するマークの種類と使い方、そして著作権マークを勝手につけてはいけないケースについて解説します。
本記事を読むことで、正しい著作権マークの使い方がわかり、コンテンツの目的に応じて正しい表記方法を選択できるでしょう。

著作権マークとは、著作権のある著作物であることを表すマークのことで、Copyrightを意味する「©(マルシーマーク)」が用いられます。
著作権(コピーライト)とは、著作物を他者に勝手に利用されないために著作権者に与えられる権利のことです。
著作権は譲渡や相続、放棄ができるため、創作者が必ずしも著作権者であるとは限りません。そのため著作権マークによって、著作権者が誰かを明記できるメリットがあります。
著作権マークが誕生したのは、各国の著作権の取り扱いの違いから生じる問題を解決するためだといわれています。
日本では創作物が生まれた時点で著作権が生じますが、かつてアメリカなど一部の国では、著作権を得るために手続きが必要でした(後述する方式主義)。
そこで、どの国においても手続きなしで著作権が保護されるように、著作権マークが制定されたという経緯があります。
なお著作権の詳細については以下の記事で詳しく解説しています。


著作権に関連するマークや、類似する他の権利を表す主なマークは、以下のとおりです。
それぞれの意味を知り、適切に使い分けましょう。
「©マーク(マルシーマーク)」は、著作権法上の著作物であることを表すマークです。「Copyright」を表す「©」と発効年、著作権者の氏名・社名の順で記載します。
コピーライトを示すマークは©マークの他、以下のバリエーションがあります
表記は異なりますが、意味はすべて同じです。「(C)」と表記されるケースがあるのは、デバイスによって「©」という記号が表示されないことがあるためです。
なお、©マークには「All rights reserved(すべての権利を留保する)」が併記されるケースもあります。これは「方式主義(後述)」を採用する国際条約(ブエノスアイレス条約)で用いられていた著作権表記の名残です。
「All rights reserved」の記載がなくても著作権は保護されるので、記載しなくても問題はありません。
CCマークは、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」を意味するマークです。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、著作者が決めた条件を守れば、作品を自由に利用してよいと意思表示するために設けられた仕組みです。インターネット時代の新しい著作権ルールとして考案されました。
CCマークを記載することで作者の著作権を保ちながら、利用者は条件の範囲内で改変や再配布が可能です。著作権者は以下4つを組み合わせることで、6種類の異なるライセンスを設定し、利用範囲を定められます。
CCマークを活用すれば、著作権者自身が決めた利用範囲内で著作物を有効に活用してもらえます。
参照:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは」
®マーク(アールマーク)は「Registered Trademark」の頭文字から取った記号で、商標登録されていることを示すマークです。
商標登録とは、自社の取り扱うサービスや商品を、事業者が他社と区別するために行う登録のことです。
日本の商標法上の商標登録表示は、登録商標の文字と登録番号で「登録商標第7654321号」のように表記します。なお、日本では商標登録の表示義務はありません。
ただし、商標登録されていないにもかかわらず、®などの商標登録表示をつけると、虚偽表示で刑事罰が適用される可能性があるため注意が必要です。
参照:e-Gov法令検索「商標法」
なお、商標については以下の記事で詳しく解説しています。

™マークは「Trademark(商標)」を表す記号です。
®マークと異なり、™マークは商標登録を受けていなくても使用できます。そのため、商標であることを明示し、他者による無断使用を防ぐ目的で、出願中だけど未登録の商標に使われるケースがあります。
類似するマークに「SMマーク(Service Mark・役務商標)」がありますが、™マークで代用できるため、実際はほとんど使われていません。
コピーOKマークは、自分の著作物を他者が使用してもよいと、著作者自身が意思表示するために使われる「自由利用マーク」の一つです。
コピーOKマークが付いている著作物は、以下の利用が認められています(紙、CD-R、ハードディスクなどいずれの媒体でも可)。
一例として、会社のパンフレットに使用しコピー・配布するケースにおいては、営利目的であっても無料配布であれば認められます。
ただし、以下の行為は認められていないため、利用の際は注意しましょう。
参照:文化庁「自由利用マークとは?」
障害者OKマークは、障害者のために非営利目的で利用する場合に限り、コピー、送信、配布などを認める自由利用マークのことです。
利用が認められる範囲は、以下のとおりです。
送信や、実費の範囲での有料配布も認められています。
一例として、障害者が利用しやすいように、障害の内容に応じて著作物を認識しやすいかたちへと改変(拡大、音声化、点字化など)することが認められています。
参照:文化庁「自由利用マークとは?」
学校教育OKマークは、学校の教育活動で使用する場合、非営利目的に限り、コピー、配布、送信などが認められる自由利用マークです。
学校教育OKマークが付された著作物は、授業のみならず部活動やクラブ活動、教員の研究会での利用も認められています。
学校OKマークは以下の利用が可能です。
送信や、実費の範囲内での有料配布も可能です。
参照:文化庁「自由利用マークとは?」

日本国内においては、著作権マークの表示は必須ではありません。ただし、海外では著作権マークを表示しないと著作権が保護されないケースもあります。
著作権の取り扱いには「無方式主義」と「方式主義」の2種類があり、国によって採用している方式が異なるのが理由です。それぞれの違いを下表にまとめました。
主義 | 無方式主義 | 方式主義 |
|---|---|---|
内容 | 登録・表示などの手続きにかかわらず、作品の創作時に著作権が発生 | 登録等の手続きにより著作権が発生 |
採用している条約 | ベルヌ条約 | ・万国著作権条約 ・ブエノスアイレス条約 |
採用している主な国 | ・日本 ・ヨーロッパ諸国 ・1989年以降のアメリカ | ・カンボジア ・ラオス |
「万国著作権条約」の方式主義では著作権マーク(コピーライト表記)の表示が義務付けられています。
日本は無方式主義の「ベルヌ条約」と方式主義の「万国著作権条約」の両方に加入しており、国内においてコピーライト表記は必須ではありません。
ただし現代のインターネット社会においては、著作物が全世界で閲覧・使用される可能性があります。方式主義の国においても著作物は閲覧できるため、インターネット上に公開する創作物には著作権マークを表示したほうがよいでしょう。
参照:文化庁「著作権テキスト」

著作権マークを記載するメリットは以下の4つです。
著作権マークの記載によって著作権の存在をアピールでき、著作権侵害の抑止効果を期待できます。
著作権マークは著作権の有無を明確にする要素となるため、表記することで誤認や無断転載の回避につながるでしょう。具体的には、以下のコンテンツと区別しやすくなります。
著作権マークがなくても著作権が認められないということはありませんが、余計なトラブルを避けるためには有効といえるでしょう。
なお、パブリックドメインについては以下の記事で詳しく解説しています。
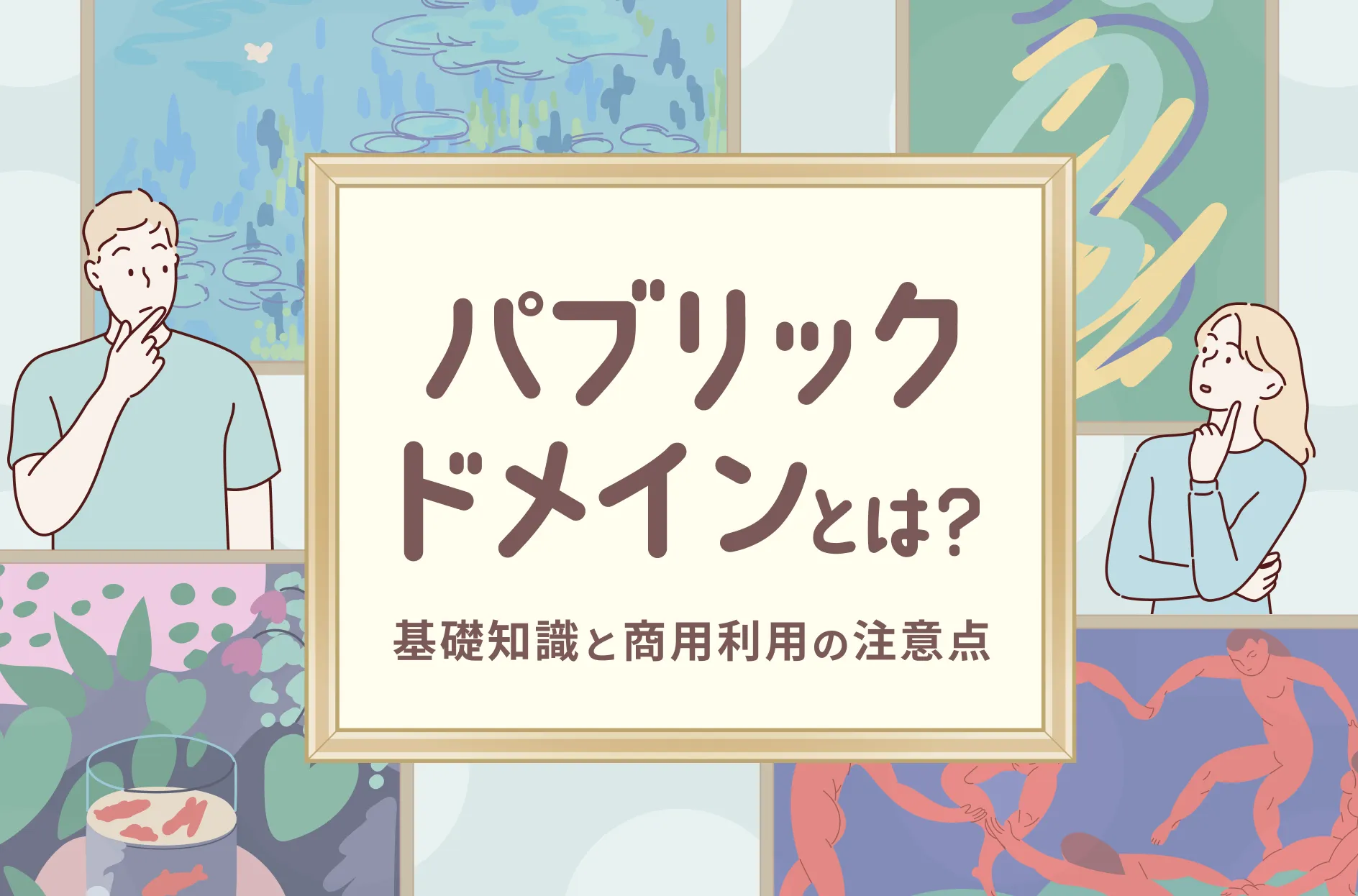
インターネット上の拡散によって曖昧になりやすい著作権所有者も、コピーライトの表記によって明確化が可能です。
SNS画像のような拡散速度の速いコンテンツは、シェアが繰り返されることによって原作者が不明になるケースが起こりがちです。
しかし、コピーライト表記をすれば、著作権所有者が周知されやすくなります。
デジタル・インターネット時代に合わせた著作権法改正については、以下の記事で詳しく解説しています。
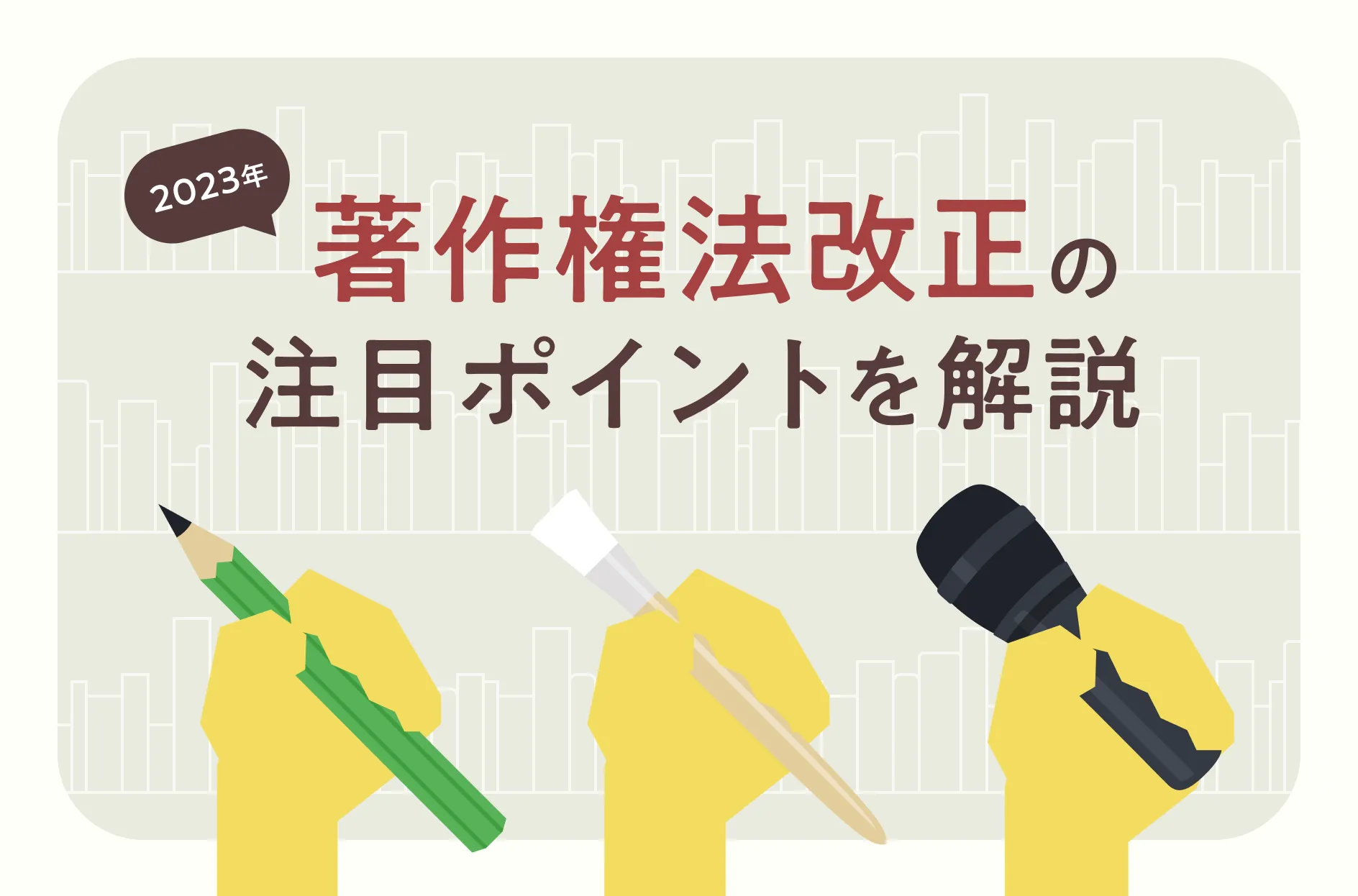
著作権マークを記載すると、「方式主義」を採用する一部の国でも著作権を主張できます。
無方式主義を採用する国においては、©マークの法的な意味はほぼありません。しかし、無方式主義を採用する国の著作物が、方式主義の国で著作権法上の保護を受けるためには、©マークの表記が必要です。
現代のインターネット社会において、©マークを記載することによって国によらず著作権が保護されるメリットは大きいといえます。
著作権マークを表記しておくことで、著作権侵害で損害賠償請求をする際に侵害者の過失の立証へとつなげられる場合もあります。
ここでいう「過失」とは、利用者が著作権についての調査義務を果たさなかったことを指します。損害賠償請求において、著作権侵害が故意か過失かが争点になった際に、著作権マークが認識しやすい適切なかたちで記載されていれば、侵害者の過失を比較的容易に立証可能です。
著作権者が訴訟に費やす労力の軽減につながるでしょう。

著作権マーク(コピーライト)の正しい書き方は「©発行年 著作権者氏名」の順です。「©」は「Copyright」「(C)」でも構いません。
著作権者の種類ごとの、表示例は以下のとおりです。
著作権者 | 表記の例 |
|---|---|
法人の場合 | ©2023 〇〇 Inc. またはCopyright 2023 〇〇 Inc. |
個人の場合 | © 2023 Jiro Tanaka またはCopyright 2023 Jiro Tanaka |
著作権者が複数人いる場合 | © 2013 Jiro Tanaka, Hanako Yamada |
海外で閲覧されることを考慮し、著作権所有者名は法人・個人を問わず英語で表記することが推奨されています。会社名も登記している正式な英語名を表記しましょう。英語で表記していない場合は以下を使用します。
また著作権を使用したい利用者が連絡を取りやすいよう、電話番号や所在地を併記をするのもおすすめです。
著作者が別の誰かに著作権を譲渡した場合は、©マークのあとに「著作者」ではなく「著作権者」の氏名を表記しましょう。たとえば制作会社が企業サイトを制作し、依頼元の運営会社へ著作権を譲渡した場合が該当します。
上記の場合は著作権は制作会社にあると解釈されないために、著作権の所在を契約書に記載しておくことが一般的です。
著作権マークの表記場所には明確な決まりがないものの、一般的にはフッターや利用規約内、画像や動画の下に書かれることが多い傾向です。
たとえばWebサイトの場合は、表示を見落とされないために、以下の場所への記載が推奨されています。
Webサイト以外についても、基本的に訪問者が認識しやすい場所に表示されていれば問題ありません。
©はどのように入力するのか、Windows・Mac・スマホそれぞれの例を紹介します。
具体的には各端末で、ショートカットキーや記号の読み方・意味の予測変換を使えば表示可能です。
OS・デバイス | 表示の出し方 |
|---|---|
Windows (MS Wordの場合) | ・Ctrl+Alt+「C」 ・「C」の予測変換 |
MacOS | Option+G(※Cでない点に注意) |
スマートフォン | ・予測変換を使い「まるしー」「ちょさくけん」「こぴーらいと」から変換 ・入力キーボード「記号」内を探す |
Windowsの場合、Word以外のソフトにおいてはショートカットキーが使えないので、他のソフトを使う際は予測変換で出力しましょう。
上記を応用することで®マークや™マークも出力が可能です。
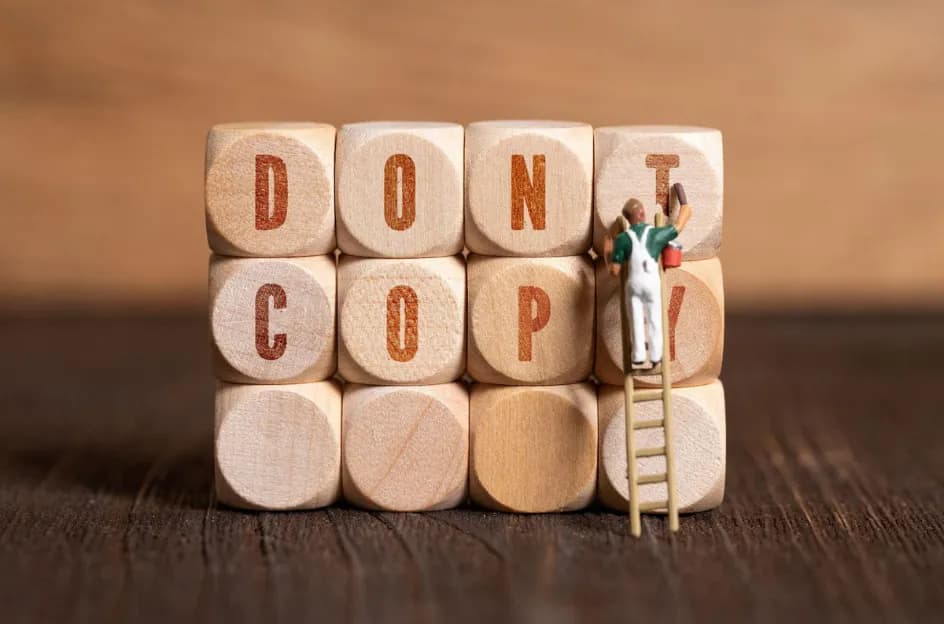
著作権マークを勝手につけることが認められないケースは、以下のとおりです。
1、2番目は原作者などの著作者がいるため、「加工」を行うには著作権者の許諾が必要です。4番目も著作権者は生徒であるため、仮にアドバイスを行った場合も、許可なく教師の著作権マークは付けられません。
3、5番目は創作した全員が著作権者となるため、独断で著作権マークをつけることはできません。創作者すべての許諾が必要です。
また5、6番目は肖像権が問題となるため、マークの表記には写っている全員の同意が必要です。
参照:文化庁「Q&A集答え」
なお肖像権については以下の記事で詳しく解説しています。


日本においては著作権マークの表記は必須でなく、マークを記載しなくても創作した時点で著作権が発生します。
しかし、著作権マークを記載することで著作権侵害を抑制でき、さらに方式主義の国においても著作権の保護を受けやすくなります。インターネット社会においては、著作物が世界中に拡散されるため、著作権マークの記載は重要です。
著作権マークの使い方を知り、適切に表記してコンテンツの著作権をコントロールしましょう。
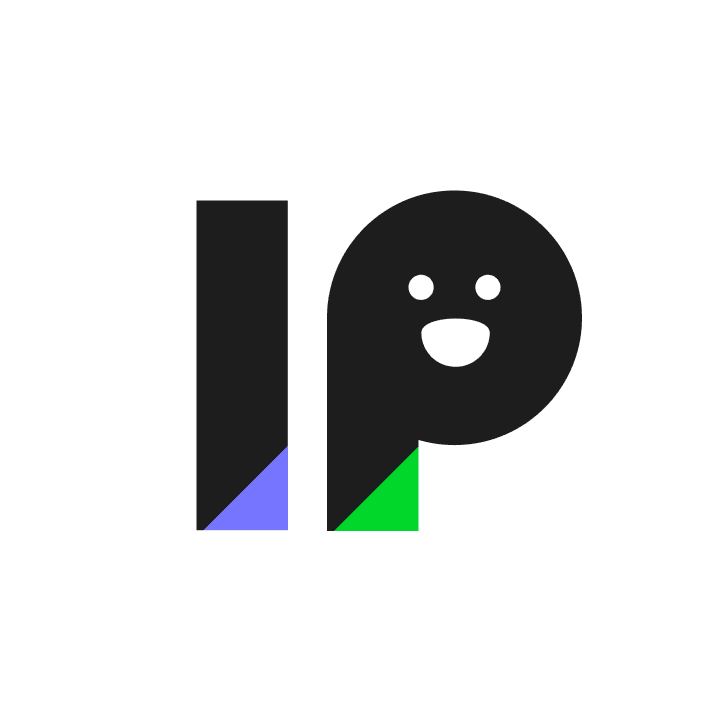
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。