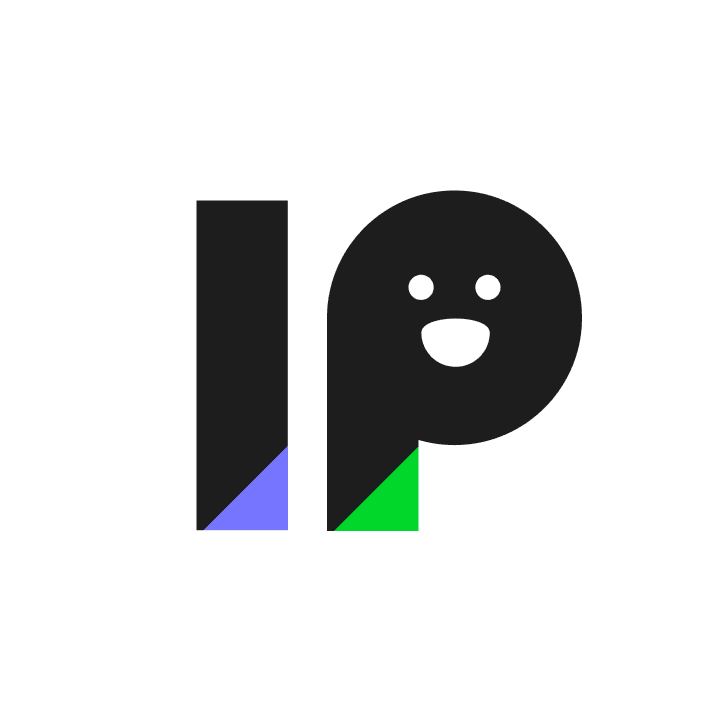
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。

「同人誌は著作権侵害と見なされる?」「同人誌を作って告訴された判例はある?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。同人誌を制作する際は、ルールを守らなければ著作権侵害にあたる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、同人誌の制作が著作権にあたるかどうか、またグレーゾーンとして扱われている理由を解説します。著作権に関する知識を深め、安全に同人誌を制作しましょう。

同人誌は、創作方法によって著作権侵害にあたる可能性があるため注意が必要です。同人誌の創作方法は、以下の2つに大きく分けられます。
著作権侵害にあたる可能性があるのは「二次創作」です。原作のキャラクターや、ストーリーなどの創作物の著作権は原作者に帰属するため許可なく改変やコピーを行うと、翻案権や翻訳権、複製権の侵害と見なされます。
それなのになぜコミックマーケット(コミケ)などで多くの二次創作の同人誌が扱われるのかというと、同人誌は「グレーゾーン」と黙認されているケースが多いためです。
のちほど詳しく解説しますが、二次創作を無許可で行った場合は、著作権者にいつ告訴されてもおかしくない状況であることを認識しておく必要があります。
ただし、私的利用の範囲で楽しむだけであれば、二次創作の同人誌を制作しても問題ありません。著作権法第30条で、私的利用を目的とする際は、著作権者の許可なしに著作物の利用が許可されているためです。
参照:e-Gov 法令検索「著作権法」
なお、著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。


同人誌がグレーゾーンとして黙認されやすい理由として、以下のような要因があります。
同人誌を通して、原作や公式作品のファンが増える可能性があるため、著作権者が黙認しているケースがあります。
同人誌などの二次創作が増えることで、より多くの人の目に触れる機会が多くなり、原作や公式の知名度が上がる可能性があるためです。知名度が上がることによって、原作の購入につながる可能性があり、新たなファンが増える場合があります。
また「同人誌を描くほどのファンは作品に愛があり、原作を支えている熱心な味方である」と捉える著作権者もいるでしょう。
同人誌界から新たな作家が生まれる可能性があるため、著作権者が黙認しているケースもあります。
同人誌をきっかけにプロの作家となった漫画家も多くいるため、作者側も出版社側も新人作家の活躍の場と甘受しているのでしょう。
世界最大級の同人誌即売会であるコミケからは、『3月のライオン』の作者の羽海野チカ氏や『大奥』の作者のよしながふみ氏など、有名作家が誕生しています。
参照: 東京新聞「『3月のライオン』作者・羽海野チカさん、コミケは「大事な灯台」 23年ぶりサークル参加の思いとは」
参照:文春オンライン「「100冊か…どうするんだろうな、これ」よしながふみさんが高3で出した初同人誌と、脳内麻薬が出た“ある体験”」
著作権侵害を取り締まるためには、告訴をする必要があり、時間と労力がかかるのも理由の一つとして考えられます。著作権侵害は親告罪なので、著作権者が告訴しなければ、法的に取り締まられることはありません。
ただし、告訴されないからといって、すべての著作権者が二次創作を快く思っているわけではありません。なかには「本当は規制したい」と考えている著作権者もいるでしょう。
同人誌における二次創作は、あくまで著作権者に「見逃してもらっている」「黙認されている」に過ぎず、「許可」されているわけではないことが多いです。

二次創作の同人誌が著作権侵害に該当する具体例は、以下のとおりです。
また二次創作物の著作権についてはこちらの記事をご参照ください。

著作権者に無許可で二次創作の同人誌を作成した場合、著作権侵害と見なされます。他者の著作物を利用する際は、著作権者の許可が必要になるためです。
原作の要素が含まれている二次創作は、著作権のうち翻案権の侵害に該当します。
利益を得ることを目的で二次創作の同人誌を制作した場合、著作権侵害と見なされる可能性が高くなります。他者の著作物を無断で使用して商業上の利益を得ることは、著作権者の権利を侵害する行為にあたるためです。
営利目的で販売した場合、著作権者から警告を受け、販売停止を求められることもあります。悪質な場合、損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。
過激な表現などで原作のイメージを著しく損なう内容が含まれる場合、著作権侵害と見なされます。とくに、以下のようなケースで法的措置がとられることがあるため注意が必要です。
著作者が自身の作品のイメージや評判を守るために、告訴に踏み切る可能性があります。さらに、名誉棄損やパブリシティ権の侵害に問われる可能性もあるため注意が必要です。
パブリシティ権についてはこちらの記事をご参照ください。
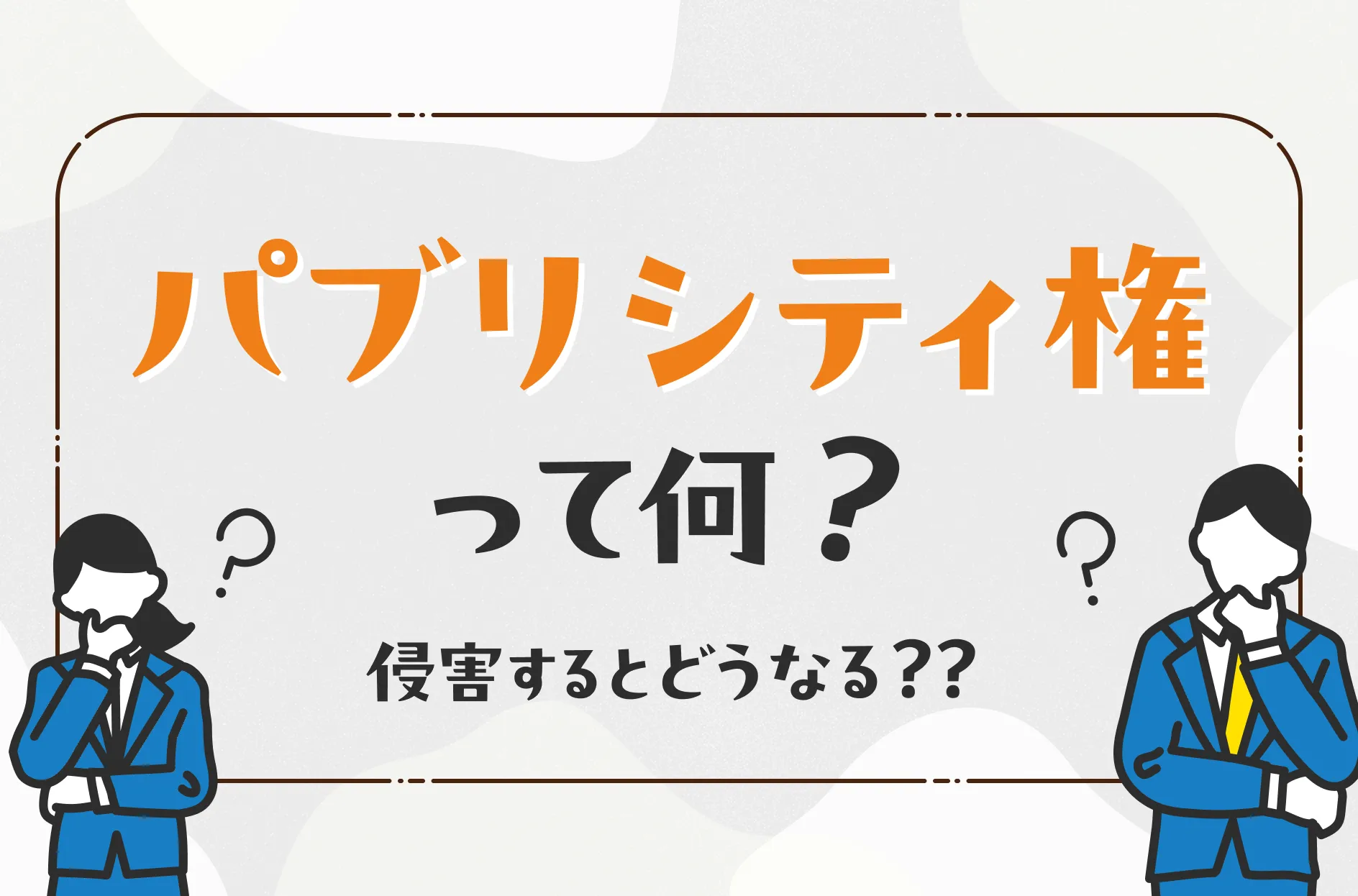

二次創作の同人誌が違法にならないケースは、以下のとおりです。
著作権者の許可を得た場合、二次創作の同人誌を制作しても著作権侵害にあたりません。著作物を利用する権利を著作権者により与えられているためです。
著作権者は、第三者に対して著作物の利用を許可する権利も有しています。第三者は許可された範囲内であれば著作物の利用が可能です。
著作権は、作品の作者もしくは出版社や制作会社に帰属します。利用したい著作物の著作権者を確認し、利用許可を得るようにしましょう。
とくに私的利用の範疇を超えて公開や販売をする場合は、事前に著作権者の許可を得なければなりません。
参照: e-Gov 法令検索「著作権法」
作品によっては他者による二次創作を認めている場合があり、公式サイトや著作権者が二次創作に関するガイドラインを明示している場合、それを遵守して創作すれば著作権侵害にあたりません。
ガイドラインの内容をよく確認し、二次創作に関するルールを事前に把握しておきましょう。たとえば、多くのガイドラインでは以下のような禁止事項が定められています。
私的利用の範囲で楽しむ場合も、著作権侵害にあたりません。著作権法第30条にて、私的利用の範囲内であれば著作権侵害にならないことが明示されているためです。
私的利用とは、本人や家族内など限られた範囲内で利用することです。同人誌を作成し、誰にも公開せずに楽しむだけであれば私的利用にあたります。
ただしその同人誌を公開してしまうと、私的利用の範疇を超えてしまいます。とくにSNS上で公開すると、たとえフォロワー数が少なくても私的利用とは見なされないことに注意が必要です。
参照: e-Gov 法令検索「著作権法」

二次創作の同人誌が、著作権侵害で訴訟された判例や事例を紹介します。
人気アニメ『ポケモン』のイメージを著しく損ねる同人誌を通信販売していた作者が、著作権法違反で逮捕された判例です。
主要キャラクターが登場するアダルト同人誌に改変し、販売して利益を得ていました。一般人からのクレームで発覚し、任天堂は「発行部数は少ないが、ポケモンのイメージを壊す内容で見逃せなかった」と、コメントを発表しています。
作者は自身の行為が違法であることを自覚しており、最終的に罰金10万円の略式裁判で有罪判決を受けました。
参照:同人誌生活文化総合研究所「ポケモン同人誌著作権問題関連」
国民的人気アニメ『ドラえもん』の「最終話」と称し、単行本を出版し販売していた男性が、出版元の小学館に警告を受けた事例です。
男性は『ドラえもん』の「最終話」と称する同人誌を書店やインターネットを介して約500円の価格で販売し、1万冊以上売り上げて利益を得ていました。この同人誌は絵が原作に非常に似ており、まるで本物の最終話のような展開だったため、小学館は男性に警告しました。
男性は不当な利益を得たことを認め、売上金の一部を小学館と藤子・F・不二雄プロに支払い、和解にいたっています。
本件は告訴にいたっていないものの、著作権をめぐる民事事件として重要な事例になりました。大きな話題となり、男性が販売を終了してからも当該同人誌はネットオークションなどで高額転売され続けています。
同人誌の二次創作の商業利用に対する、法的な監視が強化されるきっかけともなりました。
参照:朝日新聞「勝手に「ドラえもん」最終話、ごめんなさい 1万3千部売った「作者」本家に一部払う」
なお、ドラえもんの著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
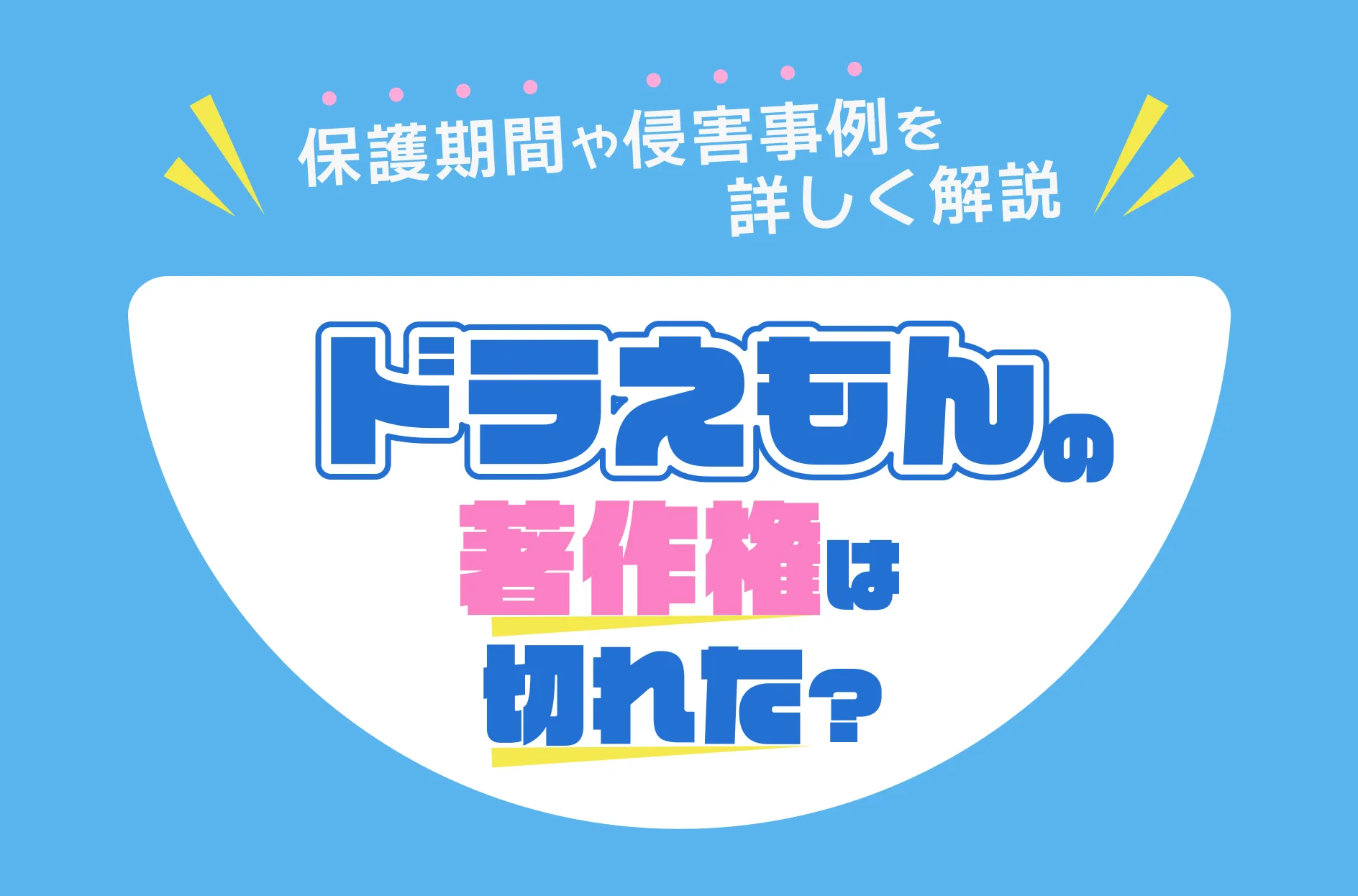

二次創作の同人誌を制作する際の注意点は、以下のとおりです。
同人誌で二次創作をする際は、二次創作に関する公式のガイドラインを確認しておくことが重要です。著作権者が二次創作を認めている場合、公式サイトなどにガイドラインを公示しているケースが多くあります。
ファンによる作品の普及活動に理解を示しているコンテンツも少なくありません。二次創作に関するガイドラインの遵守は、法的リスクを回避するための重要な要素になるため、必ず確認しておきましょう。
同人誌で二次創作をする際は、営利目的で行ってはなりません。営利目的の二次創作は、著作権の侵害だけでなく著作権者の経済的利益を奪うことになります。
多くの著作権者は、営利目的の二次創作を厳しく制限している傾向にあります。ファン活動の一環としてモラルを守り、非営利もしくは小規模利益で行わなければなりません。
同人誌で二次創作をする際は、公式作品と誤認されないよう創作しましょう。前提として、キャラクターデザインやストーリーを原作のまま利用してはいけません。
また原作のロゴデザインやトレードマークは登録商標であることが多いため、無断使用すると刑事罰が適用されます。二次創作は原作ファンに誤認や混同を与えないよう、細心の注意を払うべきです。
なお、商標についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

著作権者から二次創作物に対する警告がなされた場合は、速やかに指示に従いましょう。警告を無視すると、著作権者が法的措置を講じる可能性もあります。
最初から法的措置をとらない場合、それは著作権者の寛大な措置ともいえます。警告を受けた際の対応が、今後の創作活動にも影響する可能性があるため、適切に誠意を持って対応しましょう。

二次創作の同人誌の制作者にも著作権は存在します。二次創作物の著作者が新たに付加した部分は、独自のストーリーや設定を付け加えた「創作性」があるため「二次的著作物」として成立するのです。ただし原作を単にコピーしただけの作品、いわゆる海賊版は「二次的著作物」として認められません。
そのうえで無断で二次創作物を複製したり、無断でネットにアップロードしたりする行為も著作権侵害と見なされます。
2020年には二次創作物を無許可でアップロードされたとして、その作者が告訴した判例があります。裁判所は、原著作者の許諾のない同人誌においても二次的著作権が成立し、「権利行使として損害賠償請求ができる」と明示しました。
同人誌の二次創作にも著作権があることが認められた判例です。判例からもわかるように、「同人誌は違法に創作されたものであるため著作権はない」といった主張は認められません。
参照:文春オンライン「マンガキャラクターに著作権はない!?「BL同人誌裁判」で下された“二次創作”驚きの判決」
参照: e-Gov 法令検索「著作権法」

二次創作の同人誌活動は著作権を取り扱ううえで「グレーゾーン」と認識している人も多くいますが、著作権者の許可を得ず、ガイドラインを守っていない場合は著作権侵害と見なされます。
同人誌は黙認されているケースも多い一方、常にリスクと隣り合わせであることを忘れてはなりません。
安全に二次創作の同人誌を作るためには、著作権者の許可を取る、もしくは公式のガイドラインを遵守する必要があります。
モラルを守り、著作権侵害をしないよう細心の注意を払いましょう。
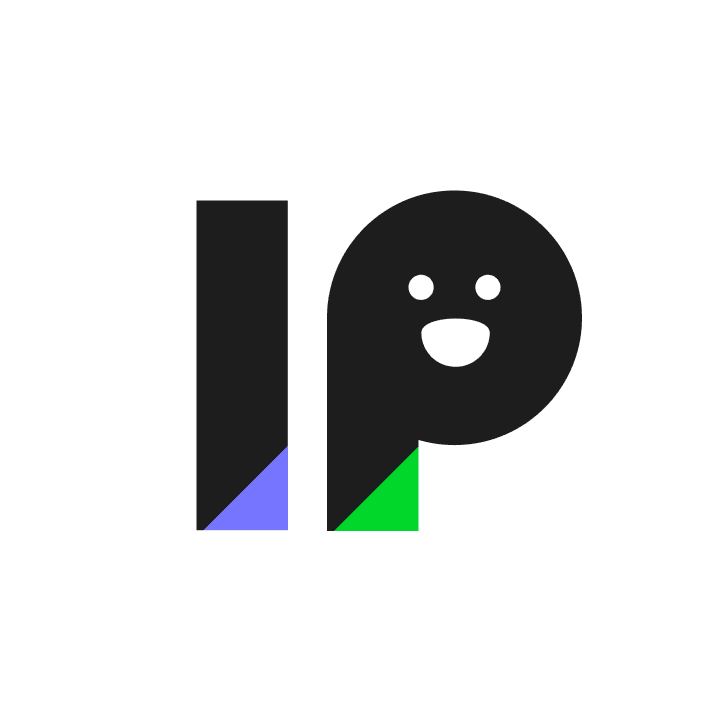
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。