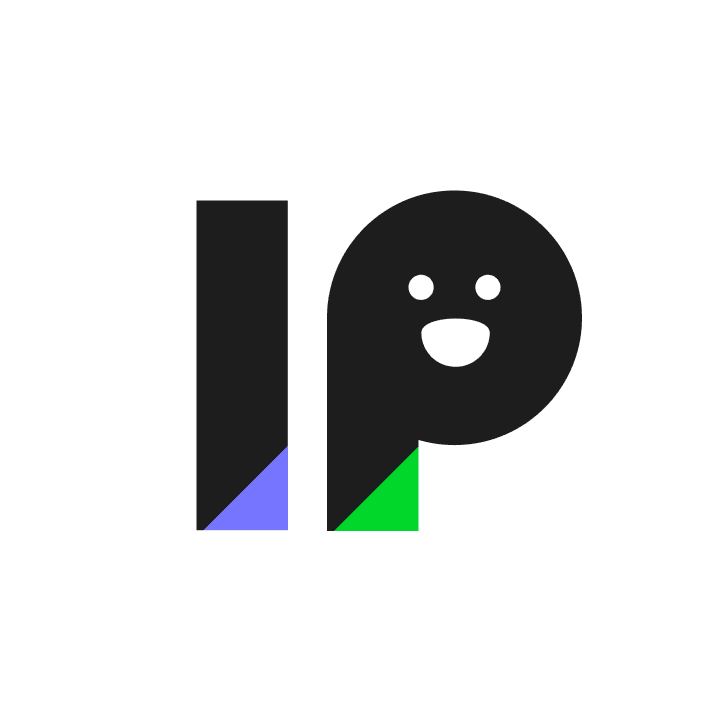
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。

「二次創作は著作権侵害にあたるのか」「どこまでなら二次創作は許されるのか」
二次創作に興味があるものの、著作権を侵害しないか心配な方もいるのではないでしょうか。二次創作は、使用する原作によっては著作権侵害になる可能性があります。過去には訴訟を起こされた事例もあるため、創作の際は十分な注意が必要です。
本記事は、二次創作の著作権について実例を交えて詳しく解説しています。二次創作が著作権侵害とならないケースや、安全に二次創作する方法についても紹介しているので、最後まで読むことで、二次創作における原作の著作権の取り扱いについて理解が深まるでしょう。

二次創作は著作権侵害と見なされる可能性が高いです。
二次創作は既存の作品を原作として生み出される作品なので、取り扱い方次第で原作の著作権を侵害しかねないからです。たとえば原作者に無断で、キャラクターのイラストを作成してSNSに公開した場合は著作権侵害にあたります。
二次創作によって著作権侵害をする危険性があるケースについて、詳しくは後述します。
二次創作で著作権を侵害すると、以下のような民事上の請求や刑事上の処罰を受けることになりかねません。
種別 | 内容 |
|---|---|
民事上の請求 | ・侵害行為の差止請求 |
刑事上の処罰 | ・10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 |
刑事上の処罰では、懲役と罰金刑の両方の処罰を受ける場合もあります。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作物を無断で使うと?」
著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。


二次創作で侵害しうる著作権と支分権は以下のとおりです。
それぞれ解説します。
二次創作で侵害しうる著作権の一つ目は、複製権です。
複製権とは、著作権者が著作物を有形的に複製する権利、もしくは他人が複製することを許諾する権利を指します。
複製の例は以下のとおりです。
イラストなどの原作を模写やトレースする行為は、複製権の侵害にあたります。ただし、イラストの練習など私的な使用にとどめている限りは、複製権の侵害になりません。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
模写する場合の著作権の取り扱いについてはこちらの記事をご参照ください。

二次創作で侵害しうる著作権の二つ目は、翻案権です。翻案権とは、著作物に変更を加え新たに創作できる権利のこと。
著作物の変更とは、以下を指します。
原作をそのまま書き写した場合が複製権の侵害であり、創作を加えると翻案権の侵害になります。二次創作は、既存の作品を原作として行われる創作のため、翻案権侵害となる可能性が高いです。
訴訟においては、原作の特徴を感じさせる部分が一致していると認められた場合に、翻案権の侵害が成立します。
二次創作で著作権侵害が認められた「出る順シリーズ事件」と呼ばれる事例をもとに翻案権侵害について後述するため、参考にしてください。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
二次創作で侵害しうる著作権の三つ目は、同一性保持権です。
同一性保持権とは、著作権者の意に反して著作物の内容や題号を勝手に改変されない権利。著作者の感情を守り、精神的に傷つけられないようにするために保護されます。
原作を無断で使用して二次創作した場合、翻案権と同様、同一性保持権の侵害についても避けられない可能性は高いでしょう。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
二次創作で侵害しうる著作権の四つ目は、公衆送信権です。公衆送信権とは、著作物を不特定多数に伝達する権利であり、インターネットなどで著作物を公表する権利。
二次創作に関係する公衆送信には、送信可能化を含む自動公衆送信が挙げられます。「自動公衆送信」は、二次創作物をSNSやWebサイトにアップし閲覧させる行為で、「送信可能化」は閲覧できる状態にすることです。
アクセスがまったくなかったとしても、投稿した時点で送信可能化に該当し、公衆送信権の侵害になります。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
参照:知的財産用語辞典「公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)」

二次創作をしても著作権侵害で訴えられることが少ない理由は、著作権侵害が親告罪であるためです。
親告罪とは、被害者が告訴することで検察が起訴できる犯罪を意味します。第三者が著作権を侵害しても、著作権者が告訴しなければ、訴訟を起こされることはありません。
著作権者が告訴しない理由には、以下が考えられます。
多くの二次創作が生まれて原作の認知度が高まることは、著作者にとってメリットといえます。また著作者自身も、かつては二次創作からキャリアをスタートしていて、理解があるケースも考えられます。
二次創作があまりに多く、訴訟を起こすとしても時間的・金銭的にコストがかかるため取り締まりきれない実情もあるでしょう。
ただし、二次創作物の影響力が大きい場合、訴訟を起こされる可能性があります。後述する「『ドラえもん』最終回同人誌事件」という、二次創作物の反響が大きかったことで訴訟を起こされた事例もご参照ください。
参照:文部科学省「著作権法における親告罪の在り方について」

二次創作による著作権侵害の危険性があるケースは以下のとおりです。
ファンアート作品を公表することで、著作権侵害となるケースがあります。ファンアートとは、ファンが原作への敬意や愛情を込めて二次創作することを指し、イラストや画像などの制作が主流です。
無許可で原作を使用したファンアートは、ファン活動の一環として非営利で公表する場合も、著作権侵害のおそれがあります。
私的にファンアートを創作するだけなら問題ありません。しかしWebサイトやSNSへアップすることで、私的利用の範囲を超えるため、著作権侵害となる可能性があります。
ファンアートについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
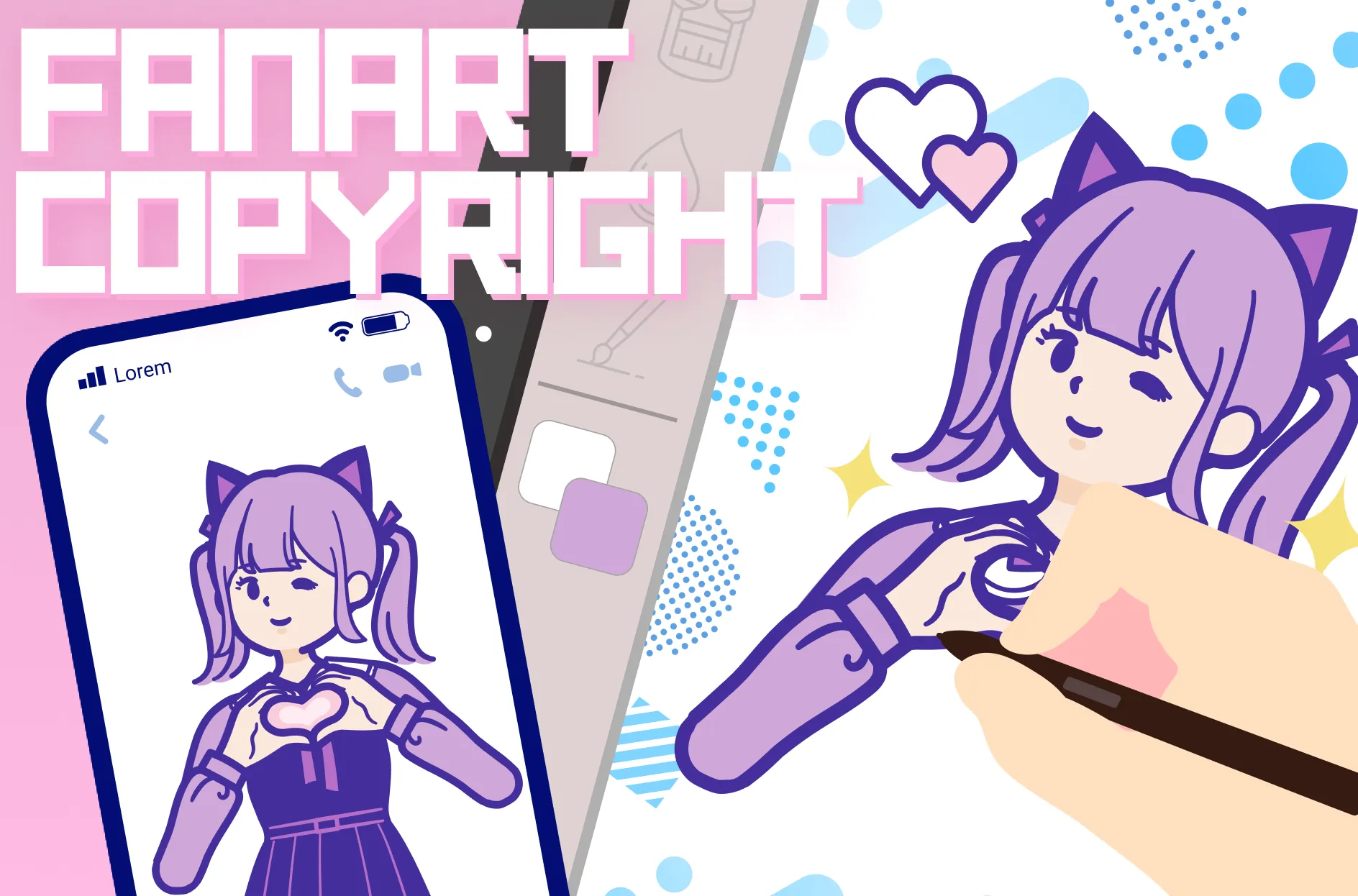
同人誌を公表することで、著作権侵害になるケースがあります。二次創作の同人誌は、元の著作物を翻案して作成していると考えられるからです。
同人誌とは、同じ思想・趣味をもつ者が集まり、創作・出版される冊子のことです。完全にオリジナルである一次創作物と、原作をもとに創作を加えた二次創作物がありますが、前者は著作権侵害にあたりません。
近年同人誌というと二次創作のほうを指すことが多いです。同人誌即売会として最大規模のイベントのコミックマーケットでは、一説によると出品物の7割以上が二次創作といわれています。
二次創作した同人誌の場合、原作の内容やキャラクターデザインをもとにした改作にあたるため、翻案と判断されます。
参照:東京新聞「「著作権」大丈夫?危ない? 二次創作が盛んなコミケの世界 権利者側は「見て見ぬふり」をしてきたけれど」
切り抜き動画を投稿することで著作権侵害となることがあります。
切り抜き動画は二次創作物であることから、著作権者に無断で作成し投稿すると、翻案権や公衆送信権の侵害にあたるためです。
切り抜き動画とは、YouTubeなどの動画配信サービスに投稿されている動画の一部分を切り抜いて再編集した動画です。独自にテロップや効果音を付け加えるなどの編集を施すこともあります。
インタビューなどの長尺動画の要点をつかんで短時間で視聴できるため人気があり、多くの切り抜き動画が公開されています。
元の動画の投稿者により、自由な創作を認めている場合や、許可制としている場合、一切認めていない場合などさまざまで、映像や音楽作品の一部を加工して制作されるMAD作品などについても同様です。
切り抜き動画の著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。


二次創作が著作権侵害とならないケースは以下のとおりです。
著作権者の許可を得て二次創作する場合、著作権侵害にあたりません。許諾の範囲内であれば、著作物が利用可能です。
原作が出版社から出版されている場合、譲渡により出版社が著作権をもっているケースがあります。一方、著作者人格権である同一性保持権は、譲渡できない権利であり、著作者に残っています。
この場合において、二次創作する際は、出版社と著作者の許諾を得なければなりません。
著作権者が原作を使用許可する際には、商用利用や公表媒体についてなど、条件を定めることが一般的です。ガイドラインでルールが示されているケースが多く、規定の範囲内で使用することが著作権を侵害しないために重要です。
二次創作が私的利用の範囲である場合は、著作権侵害とならない場合があります。
私的利用とは、自分自身や家族など、ごく限られた範囲で使用することです。しかし、二次創作物をインターネット上に公開すると公衆送信権の侵害になるため要注意です。
また不特定多数が集まる場所における公表は、たとえ利益を得ることが目的でなかったとしても、私的利用に該当しません。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
原作のアイデアを二次創作に使用することは著作権侵害になりません。アイデアは、著作物に該当しないためです。
著作物とは、思考や感情を他人が見て認識できる形として表現されたものを指します。たとえば「大きくて丸い耳の、なんでもうまくいくと楽観的な性格のねずみ」のような設定自体はアイデアです。この設定をイラストなどに書き起こすと表現になります。
アニメのストーリー展開や、登場するキャラクターの設定を使っても著作権侵害とならないのはアイデアであるためです。しかし、アイデアと表現の境界を分けることは難しいことも多く、注意が必要です。
アイデアの著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

公表された著作物を障害者の補助のために二次創作する場合は、著作権侵害になりません。
著作権法の第37条により、障害者に関わる事業者による、障害者が創作物を利用するために必要な複製、公衆送信を認めています。
障害者の補助の例は以下のとおりです。
上記のように、障害者が利用するために二次創作する場合は、著作権者の許諾が必要ありません。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
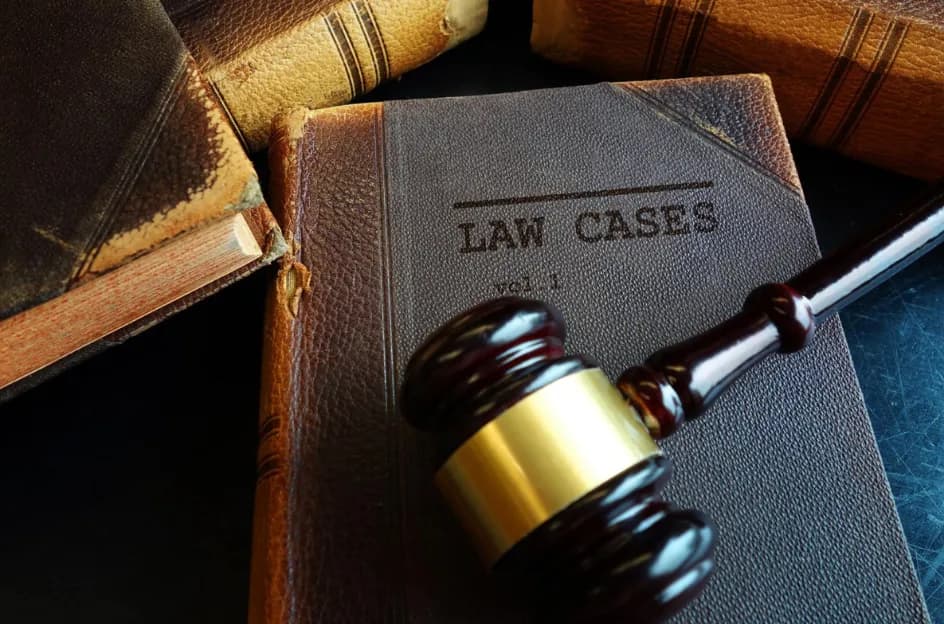
二次創作による著作権侵害が認められた事例は以下のとおりです。
それぞれ解説します。
二次創作が著作権を侵害した事例の一つ目は、『ドラえもん』最終回同人誌事件です。
37歳の男性が、藤子・F・不二雄さんの漫画『ドラえもん』の最終話と称した同人誌を2005年から販売を開始したところ大きな反響を呼び、小学館と藤子プロから警告を受けることになったため、謝罪し売上金の一部を支払いました。
同人誌は、秋葉原の書店およびインターネットで販売され、約13,000部を売り上げています。作品のクオリティが高すぎたため、本物と誤解した読者による問い合わせが小学館に殺到したことも問題になりました。
藤子プロの伊藤善章社長は「今回は一線を超えている」と話しており、このことから、同人誌の影響が大きすぎたことで警告を受けたと考えられます。
参照:朝日新聞「勝手に「ドラえもん」最終話、ごめんなさい 1万3千部売った「作者」本家に一部払う」
ドラえもんの著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
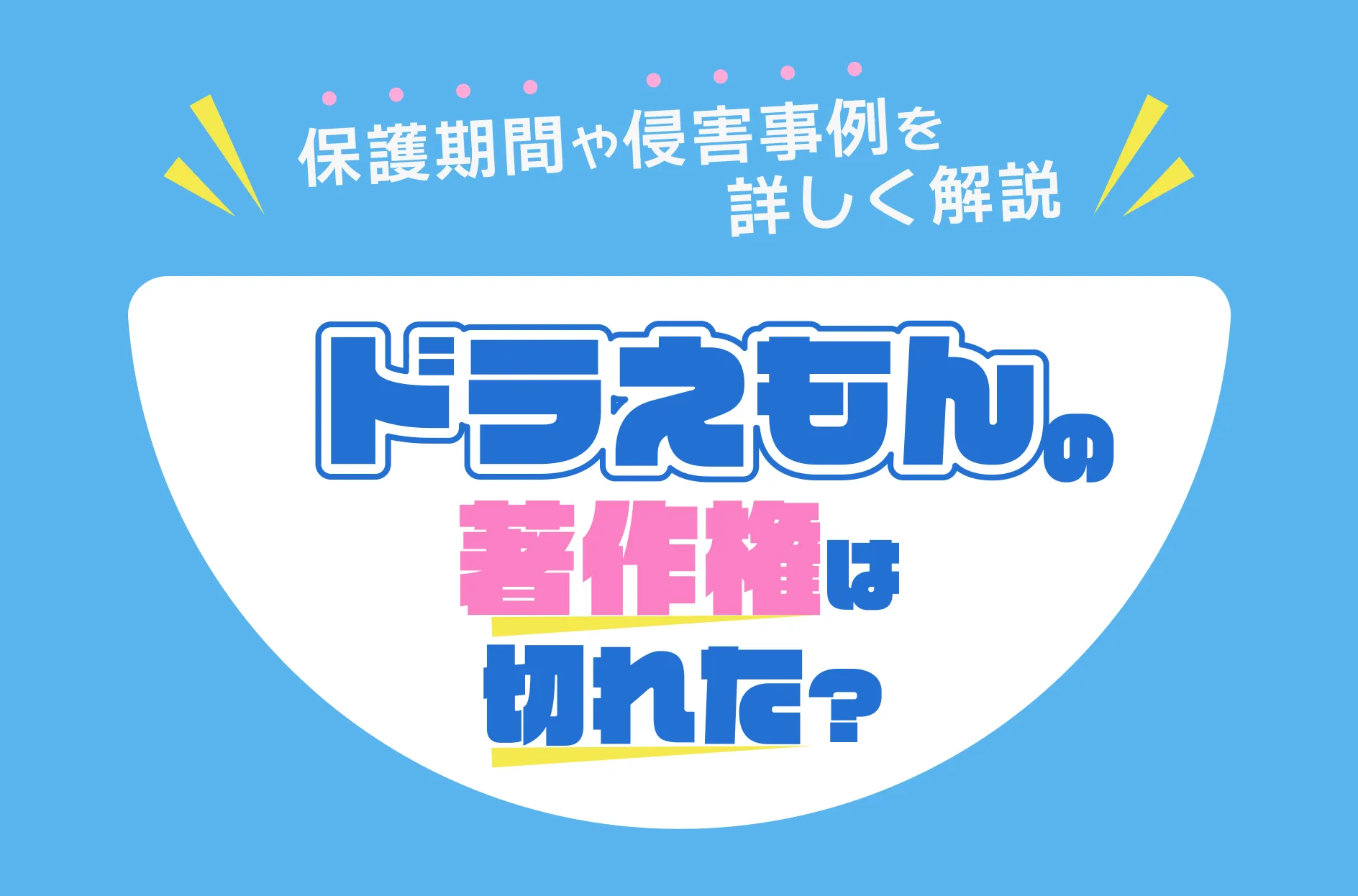
二次創作が著作権を侵害した事例の二つ目に『ときめきメモリアル』事件を紹介します。
コンピューターゲーム『ときめきメモリアル』のメモリーカードを輸入・販売した被告に対し、著作権者が訴訟を起こし、2001年に被告の上告が棄却され著作権侵害が確定しました。
メモリーカードとは、ゲームをセーブするための小型のカード状の記憶装置です。被告はメモリーカードに、主人公の能力値が高い状態でプレイできるパラメータプログラムを搭載していました。
いわゆるチートプレイが可能なメモリーカードです。判決は、ゲームソフトの改変にあたり、同一性保持権の侵害になると判断されました。被告は、原告に対し損害賠償責任を負うものとしています。
参照:最高裁判所「最高裁判所判例集」
二次創作が著作権を侵害した事例の三つ目として紹介するのは、2001年に判決が出されたスイカ写真事件です。
被告が発行する写真カタログに掲載されたスイカを被写体とした写真が、原告が発表した写真に近いものとして提訴されました。裁判所は、原告の写真は被写体の配置や背景など、いくつかの点において演出に創作性があると認めています。
被告の写真は、原告の写真の特徴的な演出部分に類似性があり、かつ原告の写真を粗雑に改変したものに過ぎないとしています。以上のことから、裁判所は被告の同一性保持権の侵害を認めました。
被告は、損害賠償および写真が掲載されているカタログの発行差止を請求されています。
参照:最高裁判所「知的財産 裁判例集」
二次創作が著作権を侵害した事例の四つ目に、出る順シリーズ事件を紹介します。
原告のイラストが、被告が出版する参考書の表紙などに使用されていたとして提訴し、2004年6月に判決が出された訴訟です。
裁判においては、イラストに使われている人形の色や形、ポーズなどに特徴があり、創作的表現と認められています。また被告のイラストに原告作品の特徴が感じられ、両者のイラストに多くの点で類似性が認められるとしています。
被告の作品は、偶然に一致したものではなく翻案物であり、著作権の侵害にあたると判断されました。
原告は、被告に対するイラストの使用差止請求および1,025万円の損害賠償請求が認められています。
参照:最高裁判所「知的財産 裁判例集」
参照:咲くやこの花法律事務所「イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?」

著作権を侵害せずに二次創作する方法は以下のとおりです。
著作権を侵害せずに二次創作する一つ目の方法は、著作権者に許諾を得ることです。
著作権者を特定し、どのような使い方をするのか、著作物の使用期間・使用範囲・使用料などを決定し契約します。
出版社など、原著作者以外が著作権を持っている場合は、原著作者と著作権者両方の許諾が必要です。原著作者に著作者人格権があり、著作権者に著作権があるためです。
著作権者が不明な場合や連絡が取れない場合、文化庁長官の裁定を受け補償金を支払うことで使用できるケースもあります。
著作権の契約の仕方については、文化庁が一般の方に向けたマニュアル『誰でもできる 著作権契約 マニュアル』を用意しています。
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作物を正しく利用するには?」
著作権を侵害せずに二次創作する二つ目の方法は、利用規約に従うことです。
著作権者によっては、利用規約内の無断使用を認めているケースがあります。あくまで、規約の範囲内で許可しているため、使用の際は十分な注意が必要です。
一例として『ウマ娘 プリティーダービー』は、二次創作に関するガイドラインを以下のとおり示しています。
“
”
引用:株式会社Cygames「「ウマ娘 プリティーダービー」の二次創作のガイドライン」
描写や表現などについて、5項目で簡潔に示しています。
著作権侵害せずに二次創作する三つ目の方法に、パブリックドメイン素材を使う方法があります。
パブリックドメインとは、著作権の保護期間が終了した作品です。日本においては、著作権の保護期間は、著作者の死後70年間とされています。
ただし著作権保護期間が終了しても、著作者人格権が残っているため注意が必要です。著作者人格権とは、著作権者の精神的利益を守るための権利です。作品の二次創作においては、著作者の名誉を傷つけないようにしなければなりません。
また、著作権以外に商標の侵害にも注意が必要です。商標とは、他の商品やサービスと区別するために使うマークを指します。
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作権は永遠に保護されるの?」
パブリックドメインや商標についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
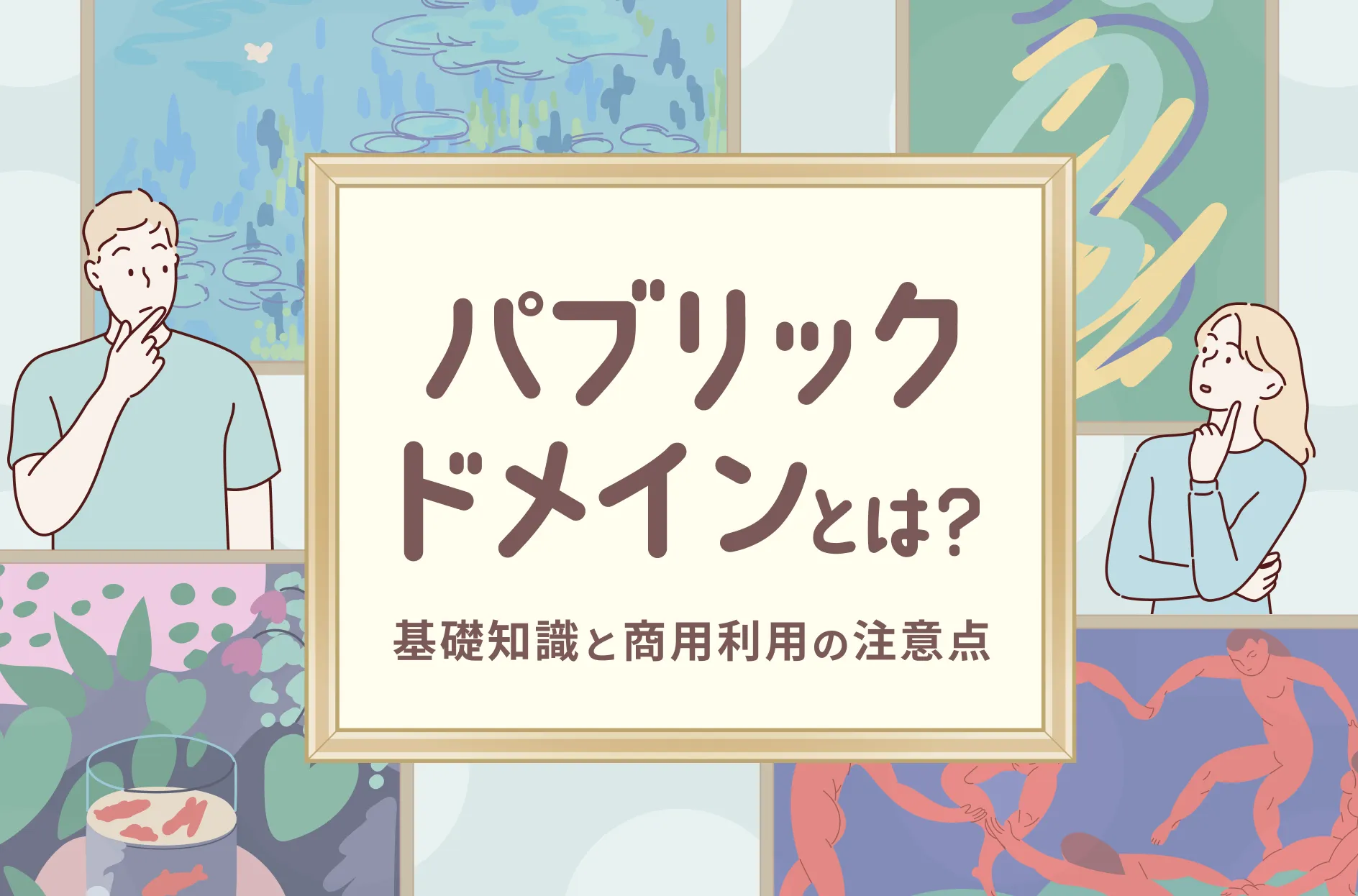


二次創作をする際は、著作権侵害に注意しましょう。二次創作において、著作権のある原作を著作権者に無断で使用すると著作権の侵害となるためです。
これほど二次創作物が出回っているのに著作権侵害となったケースが少ないのは、それが親告罪であるからだと考えられます。そのため二次創作物の発表時は見逃されていても、なにかしらの影響力を持ったときに訴訟を起こされるというケースもあるでしょう。
二次創作する際は、著作権者の許諾を得ること、利用規約に従うことが重要です。
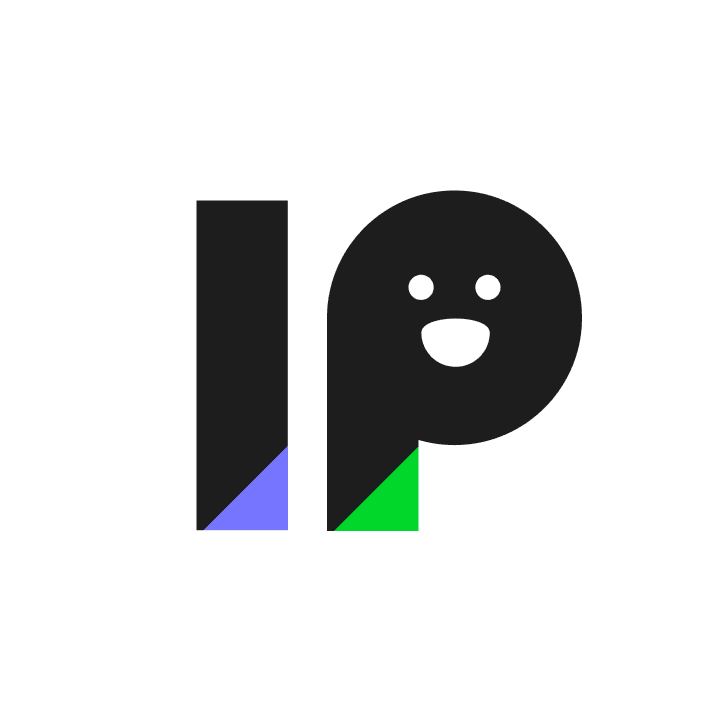
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。